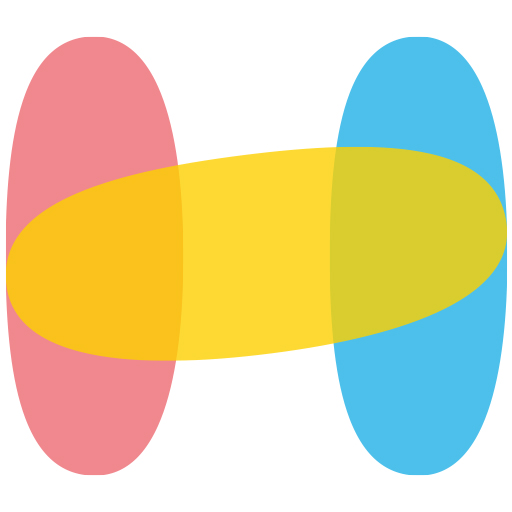一般に、病院の役割は「診断・治療」にあるとされています。他方、それ以外の役割を模索する取り組みとして、「ホスピタルアート」というものがあります。
院内に芸術作品を設置することで、患者やその家族、そして医師や看護師のウェルビーイングへの寄与を目指すホスピタルアート。たとえばスウェーデンでは、公共の建物を新築・改築する際に全予算のうち最低1%をアートに充てるよう定めた「1%ルール」が存在し、ホスピタルアートの普及が進んでいますが、日本ではまだ稀です。
数少ない国内の実践者の一人が、大阪府堺市の耳原総合病院で、チーフ・アートディレクターを務める室野愛子さん。彼女はアートの力で、病院をいかなる空間にリデザインしようと試みているのでしょうか?
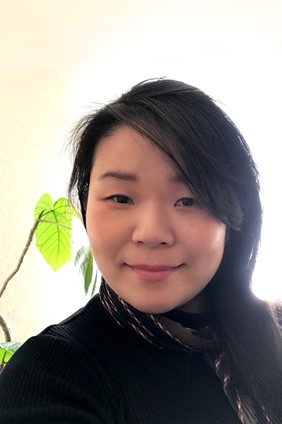
室野 愛子(むろの あいこ)
社会医療法人同仁会 耳原総合病院 チーフ・アートディレクター、NPO法人 アーツプロジェクト理事、Art & Health Design Studio 代表。
一人ひとりに表現者になってもらう
「先進的なことをしている自覚はないんです」
室野さんはインタビューの冒頭、控えめな口ぶりでこう切り出しました。
耳原総合病院は、国内では珍しくホスピタルアートを設置する病院。チーフ・アートディレクターを務める室野さんは、ホスピタルアートの普及・実践に取り組むNPO法人・アーツプロジェクトの理事も兼任しながら、院内で複数のアーツプロジェクトを企画・推進します。
プロのアーティストの作品を存分に活用し、さぞかし緻密に熟慮された空間を設計しているのかと思いきや、彼女はあくまで「ディレクション」に徹します。表現者は主に、患者や医師、そして職員や地域住民の方々。「私が大切にしているのは、一人ひとりに表現者になってもらうことです」。
実際に、耳原総合病院にはどのようなホスピタルアートが設置されているのでしょうか?
入口をまたぐとすぐに目に入る『Expectation – 希望の芽 – 』は、デンマーク在住の造形作家・Yuko Takada Kellerの手によるもので、耳原総合病院のホスピタルアートの中でも数少ない「プロのアート作品」。とはいえ、主役は地域住民です。同院は、住民一人ひとりが持ち寄った100円のカンパにより創設されたという歴史を持ちますが、そのルーツを表現するべく19,000枚のハートが組み合わされています。

その他の作品は、基本的に患者や職員、地域住民の方々の発案や制作によるものです。たとえば、病院の壁画に灯るオーナメント照明。昼夜を問わず地域を守る病院として、「子どもにも、怖そうに見えない外観にしたい」という看護師の想いが発端でつくられたといいます。

『協同の壁』

PICTURE PROVIDED BY MIMIHARA GENERAL HOSPITAL
各階のエレベーターホールやその他いくつかの箇所には、鳥や木などの絵が描かれています。この『虹色プロジェクト』は、100人以上の地域住民を巻き込んで制作されました。歴史と物語を伝えるための「継承のアート」と室野さんは位置づけます。


何人かの画家や陶芸家らの作品が展示される『地域交流ゾーン』については、「アートディレクターとしてはノータッチ」だそう。地域住民が自ら作家を選び、空間をつくり上げているのです。

新築時に加えて2019年には第3回目の募集が行われた『風の伝言プロジェクト』も、患者や地域住民の手によるものです。絵画、写真、切絵、版画、押花、布、イラスト、絵手紙を一般公募し、病院内に飾ります。もともと四国こどもとおとなの医療センターで行われていたこのプロジェクトは、「他の病院にもバトンが受け継がれてほしい」との願いが込められています。
特筆すべきは、虹が架かっていて、太陽があって……といった、見るからにポジティブな作品のみならず、一見マイナスの印象を与えそうなものも選ばれる点。人間の複雑な感情や志向性に応えるため、決して万人受けしないであろう作品も排除しません。
たとえば、職員から「怖い印象を与えるのではないか」と懸念していた猫の写真が、『昔飼っていた猫にそっくりだ』と愛でてくれる患者さんもいました」。


芸術という表現手段を健康のお供にする
これらのアートをプロデュースするのが室野さんです。詳細は後述しますが、彼女はチーフ・アートディレクターとして「やさしい院内空間づくり」を進めることで「コミュニケーションを媒介する」役割を果たしています。
室野さんが所属するのが、ES(Employee Satisfaction:職員の満足度)向上、理念の顕在化、地域交流、業務改善を目的に、2015年に発足した「アート委員会」。アートディレクターの他にも、医師、看護師、作業療法士、感染制御室、教学広報、管理事務、ボランティアコーディネーターなど、さまざまな専門職のメンバーで構成されます。
そんな彼女は、ホスピタルアートの役割を「芸術という表現手段を健康のお供にする」ことに見出します。
「自分の中にたまっている心の毒や未来への切実な希望を、はっきりと言語化するのは簡単ではないですよね。たとえば、とても悲しいときにそれを言葉にするのは、実はなかなかハードルが高い。だからこそ、アートというかたちを取ることで、それを表に出す手伝いをしたいんです。人類の長い歴史を振り返ると、喋るより歌う、文字にするよりも絵を描くことのほうが、本来は得意だったことが浮かび上がります。それぞれの人生の傍らに何らかの芸術があるという文化を、病院、さらには街全体に広めていきたいと考えています」
あくまでも主眼は、癒やすことではなく、表現すること。ホスピタルアートは治療ではありません。表現やアートを医療に活かす取り組みとしては、作業療法やアートセラピーも思い浮かびます。しかし、室野さんの取り組みは、これらとは明確に別物です。作業療法やアートセラピーは、対個人の取り組み。もちろん、ホスピタルアートでも偶発的に個々人への癒やしが発生することはありますが、あくまでも対象は空間や組織・患者さんやそのご家族も含めたまち全体だといいます。
「恥ずかしい」を乗り越えて、誰もが気軽に表現する文化を
室野さん自身は「先進的なことをしている自覚はない」と言いますが、日本国内において、ホスピタルアートがまだまだ一般的ではないことは事実です。耳原総合病院の実践で先鞭をつけ、より一層ホスピタルアートが普及していくことは、彼女が望むところでもあります。
「基本的にエビデンスベースの意思決定がなされる病院における、ちょっと自由に羽を伸ばせる領域でありたい」。
そんな室野さんの想いもあり、自らその効果測定を手がけることはしていません。
ただ、外部の研究機関によって、その効果も少しずつ明らかにされています。医療経営学者の早川佐知子は、耳原総合病院を例に、現代におけるホスピタルアートの意義を考察。音響心理学者の小松正史も、耳原総合病院の院内BGMを共同制作し、前意識的な音環境の改善に寄与していることを証明しました。
「効果がなかなか示しづらいのが難しいですよね。ぜひ私たちの実践を研究対象にしていただいて、明瞭なエビデンスが示せるようになるといいなと思っています。そして何より、ホスピタルアートの表現を経験した人が、新たな病院で広めてくださったり、家庭に持ち帰ってくださることが大事でしょう。もちろん、小児科などホスピタルアートと相性がいい領域はあります。でも、どんな病院がやるかよりも、プロジェクトを体験した人がどれだけそれぞれの領域で宣べ伝えてくださるかが、広まりやすさに直結するのではないでしょうか」
もっと言えば、室野さんはホスピタルアートそのものを通して、「恥ずかしい」という感情が表現を遠ざけてしまう日本の文化そのものを変えていきたいと意気込みます。
「私は日常生活の中で、やたらと歌うんですよね。『ちょっと待って』と言われたら、『ちょっとってどれくらい〜?♫』と口ずさんだり(笑)。何十年かかるかわかりませんが、言葉にはできない感情を取りこぼさないためにも、歌って当然、踊って当然といった文化を育みたい。まずは耳原総合病院から、『歌ってもいいんだ』『絵を描いてもいいんだ』と思える場所をつくっていきたいですね」
院内のエクスペリエンスデザインも手がける
室野さんの役割は、アートプロジェクトのディレクションにとどまりません。先ほども少し触れたように、「やさしい院内空間」の実現、いわば病院という空間におけるエクスペリエンスデザイン全般を手がけています。
たとえば、院内のコミュニケーション設計。病院の中には多数の掲示物が貼られていますが、「貼った=伝えた」と捉えられてしまい、肝心の記載情報が伝えるべき相手に十分に伝わっていないケースも少なくありません。そうしたディスコミュニケーションを解消するために、室野さんのチームは掲示物に記載すべき情報やビジュアルをデザインしています。とりわけ、オンライン面会の導入などのイレギュラーな対応が求められることも多いコロナ禍においては、きわめて重要な役割です。
そのデザインの対象は、院内に設置する家具選びや、配膳車の動線改善に寄与するシールまで、さまざまです。コロナ禍においては、アルコールに対してアレルギーを持つ人が「アルコール消毒をしていない」と批判されないように、アレルギー持ちである旨を示すバッチもつくりました。こうして幅広く院内環境の改善を手がけており、「もうごちゃまぜですね(笑)」と室野さんは言います。
ただしアートプロジェクト同様、課題発見や解決を室野さんが押し付けることはしません。自らが主導するのではなく、あくまでも職員の内発性を重視しているのです。
「私のほうから『ここは問題だから直しましょう』というプッシュはしないことにしています。あくまでもプル型に徹しているんです。私のようなアートディレクターとそのチームがいること自体はそれなりに知れわたっているので、院内のさまざまな場所で困りごとが生じたときに、相談に来てもらう存在になっていますね」
室野さんにとって、アートは「見ていると癒やされる」というだけの存在ではありませんでした。言葉にならない想いを、なんとか外に出していくための表現手段。ホスピタルアートとは、コミュニケーションの媒体だったのです。
しかし、室野さんはなぜ、ここまで人々の内発性、自己表現の補助線を引くことを重視しているのでしょうか? 後編記事では、その信念の背景にある「忘れられない体験」、ひいては彼女の生い立ちについても探っていきます。
Text by Masaki Koike / Edit by Kotaro Okada