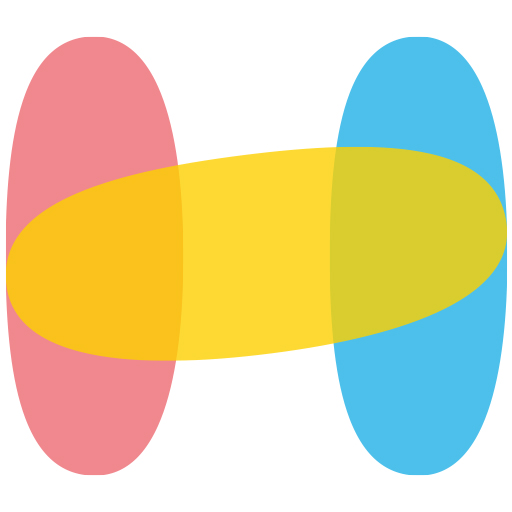個々の患者が語る「ものがたり」から病の背景を理解し、抱えている問題に対して全人的なアプローチを試みる臨床手法「NBM(Narrative Based Medicine)」。EBM(Evidence Based Medicine)が主流となっている現代において、それだけではケアしきれない領域に踏み込むための補完的な手法として、近年注目を集めています。
NBMが注目を集めるようになるずっと前の2000年代から、患者自身の「ものがたり」をベースとした終末期医療のあり方を探り続けてきた先駆者が、今回インタビューした佐藤伸彦さんです。
医師である佐藤さんは、2009年に医療法人社団ナラティブホームを立ち上げ、在宅療養支援診療所「ものがたり診療所」にて主に非がん患者への終末期医療に取り組んできました。2020年には、従来の医療の枠組みを越えたより包括的な地域との関わりを目指し、賃貸集合住宅や小売店、レンタルスペースやカフェなども併設された「ものがたりの街」を創設しています。
佐藤さんはなぜ、「ものがたり」をベースとした医療に取り組み続けるのでしょうか? 前編記事では、NBMの先駆的活動の背景にある想いに迫ります。

佐藤 伸彦(さとう のぶひこ)
昭和33年東京生まれ。 国立富山大学薬学部卒業後、同大学医学部卒業。平成2年同大学和漢診療学教室の研修医を皮切りに、成田赤十字病院内科、飯塚病院神経内科などを経て、富山県砺波市砺波サンシャイン病院で副院長として、高齢者医療にかかわる。市立砺波総合病院地域総合診療科部長、外来診療部内科部長を経て、ナラティブホーム構想の提唱者として、さまざまな支援のもと、医療法人社団ナラティブホームを平成21年4月に立ち上げ、平成22年3月19日に「ものがたり診療所」を砺波市でオープン。同診療所の所長を務める。
ある二人の死
一人助けて二人死んだ──。
医師になって三年目だった佐藤さんの身に、忘れられない出来事が起こりました。
当時の勤務先は、救急車の受け入れが多いことで知られる、とある総合病院。ある日の夕方、三十代と見られる女性が救急車で運ばれてきました。客室乗務員で、友人とインド旅行に出かけた直後だという彼女には発熱と意識障害があり、診断結果は肺炎と細菌性髄膜炎。当初は「抗生剤の投与で何とかなるだろう」と考えていたそうです。
しかし、それは「大間違いであった」と佐藤さん。その夜、ICUで痙攣を起こし、人工呼吸器の装着が必要な状況になりました。さらに、横紋筋融解症から腎不全を併発し、緊急透析も必要に。数日は予断を許さない状況が続きました。大学病院の病理学教室で働いているという彼女の夫とICUで何度も──ときには客室乗務員の仕事のことや妻である患者との馴れ初めといった個人的な話まで──話しながら治療を続け、なんとか一命を取り留めました。
そして迎えた、退院の日。車椅子に座り、帽子を深々とかぶった彼女が、夫に付き添われて挨拶に来ました。重い髄膜炎の後遺症が残っており、ほとんど一人では歩くことができず、聴力も言葉を何とか聞き取れる程度に。「そこには客室乗務員として凛々しく仕事をしていた面影は、みじんもなかった」と佐藤さんは振り返ります。
「よかったですね」
私は、退院する誰にでも言うように、そう声をかけた。
「あ・ん・ま・り」
と彼女が言った。「ありがとうございました」という言葉を期待していた私は一瞬、何を言われたのかすぐには理解することができなかった。そして「あんまり」という言葉を何度も反芻していた。それが、二人を見た最後であった。
(佐藤伸彦『ナラティブホームの物語』p5)
何とも言えない違和感を覚えながらも、日々の忙しさの中で忘れかけていたある日、警察から電話がありました。彼女がマンションの自室でネクタイを使って夫を絞殺し、自身も飛び降りて自殺をしたとのことです。「先生はあんなにがんばって一人の人を助けたけど、結局最後には二人の人が亡くなったことになるね」。先輩医師の言葉が、佐藤さんにはこたえました。
私が「治した」「救った」と思っていたものは何だったのだろう。
彼女は、あんな状態で生きていくことを望んではいなかったのかもしれない。死から救ったことが、死ぬよりも苦しい生を強いたのかもしれない。治療することが最善のこととは限らないが、治療する以外に何ができるというのだろうか…(中略)…医療の目的は、目指すところはどこにあるのか、医学と医療の違いは何なのか、そんなことを真剣に考えだしたのもこの頃からである。
(佐藤伸彦『ナラティブホームの物語』p6-7)
医師として治療するという責務を果たしたはずが、結局は命を救えなかった。それどころか、夫の命までも奪ってしまった──このとき感じた無力感が、その後既存の医療の枠組みにとらわれない実践に踏み出すことになる、佐藤さんの原点となります。
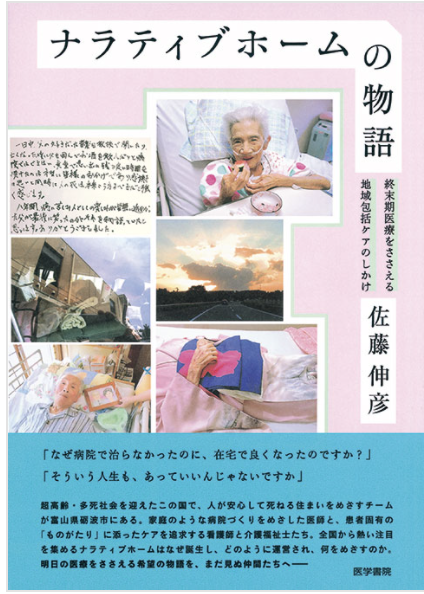
「病院という箱物の中で医療するのがきつくなってきた」
忘れられない「二人の死」、そこで感じた葛藤を胸に抱えながら、その後も医師としての活動を続けた佐藤さん。2003年、富山県砺波市で高齢者医療に携わっていたとき、市立砺波総合病院の前院長である荒川龍夫さんに「将来の夢」を聞かれ、こんな想いを口にしました。
「とにかく、もう、病院という箱物の中で医療するのがきつくなってきました。在宅でも病院でもない、あたらしい第三のアパートのようなところで、必要な医療と介護を受けて暮らしていけるようなものが、つくりたいです。高齢者の生き方に寄り添うような、医療がしたい」
(佐藤伸彦『ナラティブホームの物語』p144)
その以前から、ホスピスにも関心を持って研究会に参加していたという佐藤さん。荒川さんの助言もあり、自身の想いを夢物語で終わらせないため、いろいろな人に知ってもらえるよう文章にまとめ始めます。その中で、自身の求めているものを一言で象徴する言葉としてたどり着いたのが、「ナラティブ」あるいは「ものがたり」。その理想像を、「ナラティブホーム構想」としてまとめることにしました。
佐藤さんはナラティブホーム構想をもとに、看護師、介護福祉士、ソーシャルワーカー、医療事務、ボランティア、患者のご家族と多職種・多施設の人々を集め、隔週の勉強会をスタート。公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の研究助成を受けたり、臨床死生学で著名な哲学者の清水哲郎さんら有識者との意見交換会を実施したりしながら、構想を磨き上げていきました。
そうした末に2009年、砺波市に医療社団ナラティブホームを創立しました。同法人は、在宅療養支援診療所「ものがたり診療所」を開設。新しい病衣「スッポりん」や経腸栄養剤「マステル」の開発、カルテではない「ナラティブシート」の導入……患者さんを「関係性」の中で捉え、それぞれ固有の「ものがたり」に添ったケアを追求し、人が安心して死ねる、家庭のような病院づくりを実践してきました(同診療所の詳しい実践の軌跡については、佐藤伸彦『ナラティブホームの物語』に詳しく書かれています)。
そして、設立から10年が経った2020年秋、佐藤さんは新たな挑戦に踏み出します。ものがたり診療所に加え、訪問看護・訪問介護・診療所が併設した賃貸集合住宅、本やレコード、CDに出合える施設、日替わりでお店が変わるレンタルスペース、カフェなどが併設された「ものがたりの街」を創設したのです。
ここまで紹介した想いと軌跡を踏まえながら、今回のインタビューでは佐藤さんのその後の活動や問題意識を聞きました。
医療だけでは、地域の人々と関わりきれない
── ものがたりの街は、どのような問題意識から立ち上げたのでしょうか?
ものがたり診療所を設立し、地域の中で患者さんたちの終末期医療に携わるうちに、「これだけでは自分のやりたい医療ができない」と感じるようになったんです。70〜80代の患者さんが終末期に突然来ても、そこから人間同士の深い関係性をつくり上げることは難しい。本来は元気なときから最期まで、シームレスに関係性を紡いでゆく必要があるのではないかと。
そうした取り組みは、医療から離れないとできないと思っています。病院や診療所は、病気になるなど、ある程度「健康」からズレたときにしか行きませんよね。地域に住んでいる人たちと元気なときから関わるためには、「医療」だけをやっていては駄目。健康で、終末期医療への関心がまったくない方々と、いかにして関係性を取り結ぶのか。そのための実践として、ものがたりの街をつくったんです。
── 健康な人から終末期の患者さんまで、幅広く関われる街をつくりたかったと。
ただ、いわゆる「まちづくり」とは違います。医療・介護・福祉といった領域の人々が突然来て「まちづくりをしよう」と言い始めても、最初は盛り上がるかもしれませんが、住人の方々に冷ややかな目で見られ、失敗に終わってしまうケースが多い。
ある安斎さんに「街はつくるものじゃなくて、自然につくられていくものだよ」と教えてもらいまして。私が何か「まちづくり」の取り組みを始めたって、一時は盛り上がるかもしれないけれども、それはただの自己満足だと。その安斎さんは18歳でこの地域に来て、90代で私が看取るまで80年近く布教活動を続けてきたのですが、それでも宗教の街はつくれなかったと言っていました。そもそも、ここは伊加流伎(いかるぎ)という奈良時代から続いている地域。たかだか来て15年しか経っていない私が、「まちづくり」なんてできるわけがありません。
ものがたりの街は、WindowsやmacOSといったOSのようなものだと思っています。“プラットフォーム”と言ってもいいかもしれません。いろいろな人が“アプリ”をつくって、楽しんでもらうための場所・空間でしかない。既に健康意識が高いわけではない住民の方々が関わってくれて、何かが動き出すためのOS/プラットフォームづくりをしているんです。
高齢化社会・多死社会の“その先”へ
── ものがたりの街は、地域の人々が元気なときから最期までシームレスによりよい生を送れるようになるための、土台のようなものだったのですね。
それから、ものがたりの街を立ち上げようと思ったのには、もう一つ理由があります。ものがたり診療所はそれなりに実績を上げてきて、経営も安定してきたのは事実です。ただ、時代の流れを見たときに、次のステップに行かないと、このままでは後退してしまうと思ったんです。時代のほうが進んでいくので、現状維持だと立ち行かなくなってしまうという危機感が、最も大きな要因だったかもしれません。
在宅医療中心のものがたり診療所は、高齢化社会・多死社会において必要となる高齢者医療を求めてつくりました。でも、高齢者医療が大きな問題になる状況が未来永劫続くわけはなくて、あと数十年だと思うんですよ。2050年には日本の人口が一億人を切ると言われているわけですよね。すると、高齢者の絶対数も減っていくのは明らか。そうなったときに、たくさんつくってしまった病院や病床はどうなるのでしょうか。
高齢者医療だけに注力していると、数十年後に高齢者が少なくなって、在宅医療なども減ってきたときに、やることがなくなってしまうと思うんです。ですから、いわゆる病気の人だけではなく、障害のある人や病気の人も含めて一緒にケアしていくための場所をつくっていかなければいけないと考えています。
── ものがたり診療所が多死社会を見据えたものであったのに対して、ものがたりの街はポスト多死社会を見据えていると。
そうですね。もちろん、多死社会における喫緊の課題を解決しないと日本は駄目になってしまうので、その対応はしっかりせねばなりません。実際、在宅医療は若い医師を含めどんどん普及していますし、本人の意志を尊重し共にケア計画を立てる「ACP(Advance Care Planning)」の考え方も広まりつつあります。
最期の人を看取るということに関しては、私たちはある程度の成果と言いますか、どんな末期の人たちでも受け入れるだけの体力を培ってきています。年間60人ほど、つまり1週間に1人程度亡くなっている中でも、スタッフが疲弊しすぎず、しっかりとケアできるようになっている。ですから、次に考えるべきは、もう少し元気な人たちに向けたケアだと考えているんです。

何が「良い死」かなんてわからない
── そうして、あらゆる人たちに向けたケアを考えていくことで、佐藤さんがよく掲げている「人が安心して死ねる社会」が実現するということですね。
ただ、死ぬ瞬間が安心かどうかは、究極的にはそのときにならないとわからないんですよ。大切なのは、安心して暮らしていける社会をつくるということ。何が「良い死」かなんてわからないし、人の死に尊厳死も平穏死もないと思います。それは、死んでいく者しかわからない。ですから、それぞれの人が死までどう生きるかを考えるのが大切です。仲間や家族と一緒にいたい人、一人で静かにいたい人……それぞれが望む生き方をして死んでいけるよう、周りとの信頼関係をつくらなければいけない。
もちろん、人はいつ交通事故に遭うかもわかりませんし、100%の安心はありえません。でも、予想外のことが起こっても、「まぁここで死ねてよかったよね」と思えるような最期を迎えられるような、信頼関係をつくることはできる。ものがたりの街は、そうした関係性をつくるための場としてつくったんです。
── どうすれば、そうした信頼関係を築くことができるでしょうか?
よく考えているのが、「寛容」という言葉です。ただ、「寛大」とは違います。最近はよく 「ダイバーシティ」や「インクルージョン」という言葉で、「いろいろな人たちがいるから、いろいろな考えを受け入れましょうね」ということが語られますが、それは違うと思うんです。生きていれば、悲しいことも、絶対に受け入れられないことも経験します。それでも期待したいということが寛容ではないでしょうか。
寛容を意味する英単語「tolerance」には、「耐える」という意味が含まれています。安心して死ねる社会を実現するためには、最終的にはいろいろな人がいるけれども、それを認めたうえで、やっぱり最期に人の死はちゃんとみてあげようと、地域全体が思えることが必要です。何でもかんでも認める、ということではありません。言っていること、やっていることは絶対におかしいし受け入れられないけれど、ここで生きていくこと、その存在は最低限認めるということ。そうしないと、さまざまな事情を抱えた人々を地域の中で見ていこうとすると、すぐに疲弊してしまいます。
── ありがとうございます。次回は、佐藤さんの死や生についての考え方を、さらに深掘りさせてください。
前編記事では、佐藤さんの実践の軌跡と、その背景にある想いを深掘りしました。続く後編記事では、患者固有の「ものがたり」を大切にする医療を実践し続けてきた佐藤さんの、生と死にまつわるより深層的な価値観に迫っていきます。
Text by Masaki Koike, Edit by Kotaro Okada