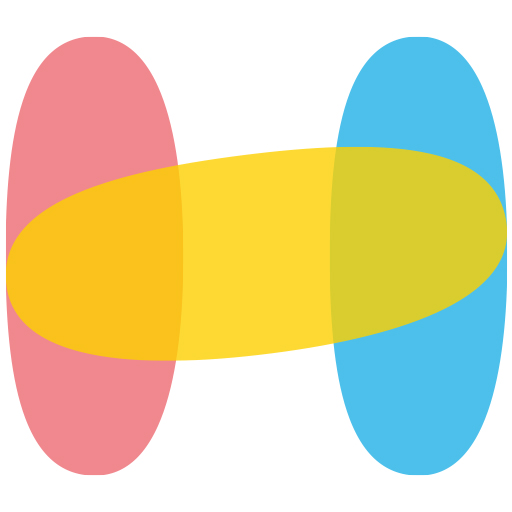医療においては、目の前の患者さんを全力で治療することが最優先。医療従事者がそうしたスタンスで仕事に取り組むことは、言うまでもなく社会にとって必要不可欠なことです。
しかし、治療行為は、すでに表出した痛みを癒す対症療法的な側面があるのも事実。その積み重ねだけで、あらゆる人々が心身共に健やかに過ごせる社会をつくっていくことには、限界もあります。医療そのものを質・量共に強化するのみならず、痛みが深まったり広がらないような、レジリエンスのある社会を育んでいくことも必要です。例えば、うつ病に罹患した人に薬物治療や精神療法を処方するだけでなく、そうした状態を生み出す社会や企業の構造を変革していくことも求められるのではないでしょうか。
今回インタビューした児童精神科医/NPO法人PIECES代表の小澤いぶきさんは、個別の治療と社会全体の変革の両方に取り組んでいます。子どもたちの権利や尊厳が大切にされる環境を育むためには、「市民性の醸成」が必要だ、と考える小澤さん。一見すると、医療とは関係がなさそうにも思える「市民性」が、どのように医療とつながっていくのか。前編では小澤さんの活動の全容と、背景にある想いに迫ります。

小澤 いぶき(おざわ いぶき)
認定NPO法人PIECES(ピーシーズ) 代表理事/ Founder /東京大学医学系研究科 客員研究員/ 児童精神科医。精神科医を経て、児童精神科医として複数の病院で勤務。トラウマ臨床、虐待臨床、発達障害臨床を専門として臨床に携わり、多数の自治体のアドバイザーを務める。さいたま市の子育てインクルーシブモデルの立ち上げ・プログラム開発に参画。 2016年、ボストンのFish Family Foundationのプログラムの4名に推薦されリーダーシップ研修を受講。2017年3月、世界各国のリーダーが集まるザルツブルグカンファレンスに招待、子どものウェルビーイング達成に向けたザルツブルグステイトメント作成に参画。
子どもが孤立しない地域をつくるため、一人ひとりを後押し
小澤さんが代表理事を務めているPIECESは、子どもが孤立しない地域をつくるプログラム「Citizenship for Children」(以下、CforC)を展開しています。
安全に頼れる誰かがいない環境で、子どもが他者や社会への信頼を失っていく「子どもの心の孤立」の問題が深刻化するなかで、支援機関や学校など、子どもの生活や学びを支える主な担い手の逼迫化が課題となっています。
そうした状況で、子どもたちが生きる地域に信頼できる大人を増やし、子どもと自分、そして地域のウェルビーイングを耕していくため、2019年より実施しているプログラムがCforC(前身となる「コミュニティユースワーカー育成プログラム」は2016年より実施)です。オンラインでの講義やワークショップを通じて、地域に暮らすさまざまな背景をもつ子どもたちの周りで、柔軟で主体的なアクションが生まれる「土壌づくり」を行っています。
プログラムは大きく3種類。まず、自分自身や子どもの感情、地域や社会の出来事をありのままにみつめていくためのまなざしやマインドセットを「みつめるコース」。そして、子どもや地域などでの実際の関わりをもとに自分の感情や価値観、目の前の子どもの感情や価値観に目を向け、チームで問いかけながら、自分のこと、子どもや他者との関わりを丁寧にリフレクションしていく「うけとるコース」。さらには、実際に地域で自分の願いを振り返りながら、自分にとっても子どもにとっても地域にとっても、ウェルビーイングなアクションをしていくためのまちづくりや市民性についての探求までカバーする「はたらきかけるコース」です。
CforCは現在、茨城県の水戸地域、奈良県の大和高田市、東京都の複数の地域での展開に加え、地域横断のプログラムも実施しています。大学生から、60代の方々まで幅広い年代、かつ子どもに関わる専門職から「空いた時間で何かしたい」という人まで、属性やモチベーションもさまざまな人たちが参加し、約半年ほどかけて、実際のプロジェクト立ち上げに伴走します。
プログラムの結果、その人の暮らす地域や企業でのコミュニケーションにおける小さな変化が起こっているのはもちろん、子どもと同じ地域の参加者がつながって、自分を表現できるものづくりの場が生まれて、そこが子どもの居場所となっていくなど、参加者は地域のさまざまな変化を実感しているとのこと。
さらには、地域のさまざまな人と協力しながら、子どもたちがふらっと立ち寄れる駄菓子屋や、助け合いの場の情報やコラムを掲載した新聞の発行など、9つほどのプロジェクトが立ち上がっています。たとえば水戸地域でのプログラムに参加してくれたコンビニのオーナーさんは、コンビニを通して出会う子どもたちの背景を想像しながら、何かできないかと考えていました。そこでイートインスペースを開放し、ボードゲームや本などを置きました。子どもたちと一緒に、子どもたちが気軽に遊んだり学んだりできる場所をつくっていったと言います。結果、地域の方々が子どもたちに声をかけたりと緩やかな繋がりが生まれたと言います。「生活の綻びと出会う場所」でもあるコンビニならではのアプローチを取ったのです。
「『自分がいてもいいんだ』と思えて、生活の動線にあるコンビニだから受け取ることのできる子どもたちのニーズや願い、サインがあります。その背景を考え、何かできないだろうか、と考えて生まれた子どもに、そして、地域に開かれた「こころコンビニ」。地域の人に声をかけたり、場所をつくったりするのは、一人では難しいこともあります。CforCでは、チームで学び合い、エンパワメントし合える仲間がいることで、お互いがお互いの一歩の後押しをしていたりもします」

「見つめる」「受け取る」「働きかける」から成り立つ市民性
小澤さんのこうした活動の根っこにあるキーワードが「市民性の醸成」です。市民性に根ざしたウェルビーイングの実現を、PIECESの組織のとても大事なコアに置いているといいます。
「いわゆる国に紐付いた市民性ではありません。『Citizens of the world』という感覚があります。『見つめる』『受け取る』『働きかける』というプロセスを経て醸成される新しい市民性が、これからの時代に必要だと考えています。私自身もそうですが、自分が生きてきた経験や環境の眼鏡で、自分や社会の中のできごとを見つめてしまいがちですよね。その眼鏡や自分の価値観をちょっと脇に置いて、ありのままに起こっていること、自分や人々の真のニーズや願い、押し殺してきた感情を、関心や好奇心を持って改めて『見つめる』。すると、ふだんは気づかないようなことを発見したり、感受したり、改めて社会や世界で起きていることを『受け取る』ことができる。社会で起こっていることは何らかの形で自分が影響を及ぼしています。だからこそ、自分の振る舞いが社会でもあるし、自分の表現が未来をつくっている。今社会と共鳴しながら、見つめ、受け取ったものを大切にしながら、自分なりのかたちで『働きかける』──これが私たちの考える『市民性』です」
小澤さんは、この「見つめる」「受け取る」「働きかける」のプロセスが実践された例として、CforCの参加者に起こった出来事を紹介してくれました。公園で、子どもに対して気になる関わりをしている人がいて、普段なら「どうしたらいいかわからないから通り過ぎよう」となっていたところを、「その人にも何か困っていることがあるのかもしれない」という眼鏡で捉え直し、その人に話しかけてみたそうです。そうした小さなことでも、見つめ直すことで気づく見えていなかったことや、メッセージがあると、小澤さんは言います。自分の身近でできることから、市民性の発揮を後押しをしているのが、CforCのプログラムなのです。
もちろん、政策や法律といったシステム面を整備することで、問題に対してアプローチをしていくことも必要です。でも、それだけだと片手落ちになってしまう。子どもが権利主体であることを法律で保障する「子ども基本法」の制定を政策提言するなど、アドボカシーをはじめとした制度面でのアプローチを行いながらも、CforCで社会をつくっていくソフトでもあり、OSとも言える市民性を醸成する。システムとマインドセットの両輪が社会に兼ね備わるように働きかけているのが、小澤さんの活動です。
「構造的なシステムと、社会を生み出す人びとの心の持ちよう。この両輪が大事だと思っています。地域は課題やニーズのるつぼでもあります。そこに暮らす私を含めた市民一人ひとりが柔軟に動き、多様なソーシャル・キャピタルが生まれてこそ見えてくる、出会う声がある。動的な社会関係があるからこそ生まれるセーフティネットがある。それがあって初めて、市民性に根ざす政策がつくられもするし、機能もすると考え、まずは市民性の醸成に取り組んでいます」
葛藤を乗り越え「それぞれのウェルビーイングの共存」へ
「見つめる」「受け取る」「働きかける」という要素で構成される、新たな市民性の醸成を掲げ、CforCを展開しながら構想しているのは「それぞれのウェルビーイングが共存しあえる社会」です。
「客観的な指標としてのウェルビーイングもありますが、ウェルビーイングって、とても主観的なものでもあると思うんです。個々人の心や身体にとって、ちょうど良い感じの状態。自分にとってのそうした状態は、ときには誰かのウェルビーイングを阻害することもある。だからこそ対話や関わり合いを通して、それぞれのウェルビーイングが共存し合える状態を探求し続けていくことが、市民性に根ざしたウェルビーイングの社会につながる。そう考えて、実践を続けています」
CforCでは、身近での小さなアクションを通じた対話と学習のための基盤として、「リフレクション」を重視しているといいます。自分がこんなことを話し、相手がこうやって応答し、自分はこんなふうに感じた……自分自身の関わりをすべて可視化してもらい、それによって行動の裏にある自分や相手の真の願いを知っていく。そうしたリフレクションと地域での経験や仲間とのやりとりの積み重ねにより、自分への気づきの目が生まれ、起こっていることへの眼差しが変化し、心や身体が開き起こっていることをセンスして受け取り、心から社会に働きかけていく。そうやって市民性が醸成され、「それぞれのウェルビーイングの共存」が実現していくといいます。
「対話や学習を続けていくプロセスには、葛藤しかないような気すらします。自分はこれを願っていて、相手はこれを願っていて、子どもはこれを願っていて……そこにコンフリクトが生じることは多い。葛藤が生じるのは、自分の中にちゃんと社会があるからこそなのではないでしょうか。だからこそ正解がわからない中、葛藤を抱えながら一歩を踏み出すとき、葛藤を共有したり、その葛藤も大切なリソースであり、レジリエンスであると捉えてエンパワーメントしあえたりする関係性が必要です。それをチームや集団で実現することは、CforCでも大切にしていますね」

「誰かの痛みで成り立つ社会」への疑問を抱いた幼少期
小澤さんはなぜ、医師であるにもかかわらず、「市民性」にここまで強い想いを抱くようになったのでしょうか? その原点は、山梨県の山間部で育った幼少期にまで遡ります。
「保育園のときに、いつも優しい先生が毛虫を毛虫というだけで踏み潰しているのを見て、衝撃を受けたんです。その後も『はだしのゲン』や手塚治虫の作品を通して、人が人以外の生物にしていることを、ジェノサイドのような形で人に対しても行っていると知って驚きました。そうしてコンフリクトや誰かの排除、何かや誰かの大きな痛みの上で社会が成り立っていることへの疑問を強めていき、それぞれの安全や安心が共存するあり方がないかと考えるようになりました」
その後、「表には見えない人の心が引き起こしていること」への関心から、児童精神科医になった小澤さん。子どもの心のケアに携わっていくなかで、身体と同じように心もケガをすること、そして子どもの心の傷は、社会の歪みがしわ寄せられた結果であることに気づきます。
医療で傷を治し続けるのも大事だけれど、戻って暮らす地域や社会が痛み続けていたら、結局は子どもたちはずっと傷を抱え続けるのではないか──そんな想いを抱くようになり、社会全体のレジリエンスや集団の傷の癒しへと、興味が移り変わっていきました。そして「集合的トラウマ」(大人数の集団が心の痛みを経験したときに、構成員たちの中に広がる感情的なつながり)をテーマにリサーチを続けていくなかで、いろいろな人たちと一緒につくる健やかな社会のあり方に関心を持ったのが、CforCの出発点です。
「健やかな状態って、誰か一人がぐいっと引っ張ってつくるというよりは、一人ひとりの手元からつくられていくものだと思うのです。社会を生み出している人々が健やかじゃないと、結局、健やかな社会はつくれない。そうした状態を可能にする、一人ひとりの手元にあるウェルビーイングのかけらや働きかけを『市民性』と捉え直し、現在の活動に至るようになりました」
前編では、小澤さんが代表理事を務めるPIECESが運営しているCforCがもたらしている社会変革、その根底にある、幼少期より徐々にかたちづくられた「市民性」──「見つめる」「受け取る」「働きかける」──への想いを掘り下げました。続く後編では、医療と「市民性によるケア」がグラデーションになっていくこれからの社会像と、その中で「共に進化する存在」として医療が果たすべき役割に迫ります。
Text by Masaki Koike, Edit by Kotaro Okada