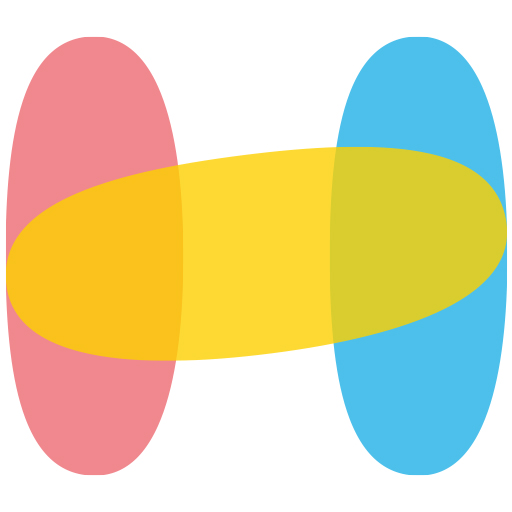人々が健やかで幸福な生活を送れるようになるためには、医療によって患者を治療することだけではなく、痛みが深まったり広がる前に誰もがケアしあえたり、痛みが深まりづらい社会になるよう、社会構造に働きかけることが必要です。
誰もが互いにケアしあえる社会が実現したとして、そこでは医療はもはや不要となってしまうのでしょうか?
今回インタビューした小澤いぶきさんは、児童精神科医でありながらNPO法人PIECESの代表も務め、「市民性の醸成」というキーワードのもとに、誰しもの存在が大切にされる社会を目指し、子どもが孤立しない地域社会の実現に取り組んでいます。前編では、小澤さんが代表理事を務めるPIECESがもたらしている社会変革の全容、その根底にある、幼少期より徐々にかたちづくられた「市民性」──「見つめる」「受け取る」「働きかける」──への想いを掘り下げました。
後編では、「市民性の醸成」を積み重ねた結果として、小澤さんが構想している社会像に迫ります。医療と市民性によるケアが両立する社会に向けて、医療が果たすべき役割とは何でしょうか?
サービスや医療からはこぼれ落ちてしまう領域
いわゆる国に紐付いた市民性ではなく、「見つめる」「受け取る」「働きかける」という要素で構成される、新たな市民性の醸成を掲げる小澤さん。自身が代表理事を務めるNPO法人PIECESで、子どもが孤立しない地域をつくるプログラム「Citizenship for Children」(以下、CforC)の活動に精力的に取り組んできました。彼女は自らがアプローチする領域を「サービス化するとこぼれ落ちてしまう領域」と表現します。
「市民性に基づく関わりは、供給側と需要側といったかたちでサービス化されたり、貨幣価値だけというような一つの価値だけで評価がなされることが難しい領域でもあり、サービス化や一つの価値への固定化により、つながりの格差が生まれてしまう可能性があると思っています。ですから、この領域は、いわゆる支援と被支援、サービスの供給側と需要側といった構造にはしないほうがいいのではないかと考えています。とても偶発的で、身体性も伴う感覚的な領域なので、固定化した静的な枠組みを与えようとしても、こぼれ落ちてしまうと思うんです。異なる価値観や役割を持つ集団同士にとっての中間集団としての役割を持ち、だからこそ、既存の構造の中での役割や価値観をあくまで自分の中の多様性の一つとして認識し、一人の人として関わり合えることが大事だろうと考えています」
そうした曖昧さをはらむ領域だからこそ、短期的な成果を出すのは容易ではありません。それに伴い、活動のための資金を集めることも大変になります。それでも小澤さんは、長期的なインパクトを見越した関わりを模索してくれる地域の企業や団体と一緒に活動を続ける道を探し、プログラムを体験してもらうなかで価値を伝える取り組みを地道に続けています。
現在も少しだけ続けているという児童精神科医としての臨床は、今後も続けていくと小澤さん。「医療現場はいま一番痛みを抱えている声やそれが生まれた社会の構造の歪みと出会う場所でもあり、外部化し他人事とせず自分のこととして大切に受け取り続けていきたいです」。

心の医療にも、医療と市民性のグラデーションを
そうして「サービスや医療からはこぼれ落ちてしまう領域」へのアプローチを続け、社会全体のレジリエンスが高まっていくと、「医療と市民性のあいだのグラデーション」が生まれると小澤さんは見ています。
そうしたグラデーションは、身体については既にある程度できあがっています。例えばちょっとした擦り傷への対処法は誰もが子どもの頃から知恵として手にしている一方で、複雑骨折をしたり交通事故に遭ったりしたら「さすがに自分では対処できないから病院に行こう」と思うでしょう。また30年前には知られていなかった熱中症というものが知られてからは、予防できるようになりました。
こうした状況が、現状では症状や対処法が見えづらい心の分野についても起こっていくのではないかと小澤さん。
「市民一人ひとりの可能性やレジリエンスに目を向けていくことで、心も、それぞれの存在ももっと大切にしあえて、結果それが心の分野の予防にもなっていくのではないかと思います。医療者が持っている専門知化された心に関するケアを、もう一度市民の手に取り戻していく。例えば危機などのストレスを受けたり、日々負荷がかかることがあったりしたときに、それによって何が起こるのか、どんなケアができるのか、どんな環境があったらいいのかということを学びながら、ケアの仕方がわかるようになっていく。一人ひとりが何らかの危機に対処してきた知恵もあるはずです。その知恵も大切にしながらケアを再構築していく。心の傷が生まれやすい環境で、さらに心が傷つき、心が複雑に傷を負って病院に行くといった、医療と市民性が断絶した状態に、グラデーションが生まれるといいなと思っています」
小澤さんがそう考える背景には、専門である児童精神科における医療リソースの逼迫もあります。トラウマケアも専門家がそこまで多いわけではなく、子どもの心、家庭など、それぞれのジャンルでソーシャルワーカーをはじめとした専門家の数が不足しているといいます。こうした状況に対して医療を充実させていくことも大切ですが、一人ひとりの手に「心の健やかさへの知恵」を取り戻していくことも重要だ、と小澤さんは考えます。
「自分たちの手にもう一度、心のあり方の選択肢を取り戻していくことだと思っています。医療とそれ以外のケアがもっとシームレスになるといいなと」
小澤さんの考えと近い概念に、薬ではなく地域のつながりで社会的孤立に対処する「社会的処方」というものがあります。ただ、それとは通じる点も多い一方、違う側面もあるかもしれないと言います。
「社会的処方の仕組みにおいては、リンクワーカーや医療が働きかけて地域のさまざまなつながりやアクティビティを処方していくと考える一方、市民性の醸成は、傷ができたときに、いろいろな細胞が集まってきて、それぞれの役割を個々が果たしながら癒していくようなイメージでしょうか。完璧にオーガナイズされきっているというよりは、動的な文化としての社会的処方のようなものと近いかもしれません」
医療は「共に進化する」存在へ
医療と市民性のグラデーションが生まれた世界において、医療はいかなる役割を果たすのでしょうか? 市民性によるケアの領域が広がっていった末には、医療の果たすべき役割はもはやなくなってしまうようにも思えますが、小澤さんはそう見ていません。リンクワーカー的な人、予防的な社会的処方を生み出す人……地域の中でいろいろな役割が自律的に生まれていっても、より専門的な治療を必要とする人の心や病に関する知恵や知識と、それを生み出す社会の構造との出会いは、しばらくは医療にも集まると見ています。なぜなら、医療はより困難な傷、より高度な病のニーズに応えるようになっていくはずだから。医療従事者自身も学び続け、そこで得た知恵や知識を市民のもつ知恵や知識と交わし合いながら、お互い学び合い、手渡し、共有していく存在になると、小澤さんは考えています。
「いま地域にはどんなニーズがあり、医療はどの役割を担うべきなのか。医療は地域の中で対話しながら、共に進化していく存在になるのではないでしょうか。そもそも、医療者も一人の市民です。専門家としての立場、既存の権威構造の中で内在化してきた権威から一度降りて、一人の人間として市民性を発揮する仲間として集い、その後で再び医療に戻る。そうすることで、見えてくるものがあるのではないかと思います」

病は社会の問題の表出にすぎない
そうした役割を果たしていくため、一人ひとりの医師には「患者さんを例えば、『病を持つ人』『弱った存在』といった一元的な見方をしないこと」が求められると小澤さんは言います。
小澤さんは児童精神科医として臨床に取り組む中で、病が目の前の患者さんの問題として捉えられる構造に疑問を抱いてきました。その子どもの負っている傷は、社会の構造によって引き起こされたはずなのに、なぜ“その子”が薬を飲んだり、病院で拘束されたりしなければいけないのだろう──問題を個人化する構造に、違和感を覚えていたと言います。たまたま脆弱な環境に置かれていたがために、社会の問題のしわ寄せを引き受けている人たちを「弱い人」と見ることはおかしいのではないか、と。
患者と「対人(たいひと)」として出会ったときに、その人にたまたま表れているものを社会の問題だと再定義し、捉え直すこと──それこそが、小澤さんが考える、これからの精神医療のあり方です。個人の病気だという眼鏡でしか捉えていないと、問題は個人化してしまう。集団の痛みや心の傷といった眼鏡をかけたときに初めて、その人が生きてきた地域で起こっている歪みや社会の問題に、目が向くはずだと言います。
「患者さんと一人の人として出会い直し、その人の痛みに耳を傾け、受け取り、そこから社会の問題をひもとき、社会全体に還元していく。その問題と関わっている人たちと対話しながら、問題を手渡し、協働していくことが大事でしょう。医者と患者という構造から降りてナラティブを再構築し、その構造に加担している自分たちのあり方を振り返り、当事者の方々とともに社会の痛みが癒されるあり方をつくっていく必要があるのではないかと考えています」
小澤さんは最後に、これからの医療が果たすべき役割としてもう一つ、「ストレングスやレジリエンスを育むこと」を付け足してくれました。
「いま児童精神科の領域では、『トラウマインフォームドケア』という取り組みが行われています。危機が起きたときに、私たちにどんなことが起こり、心にどう影響するのか。これまでの危機の影響を受けて、その人や自分にどんなことが起きているのか。そこに対して何ができるのか。そして繰り返される危機による心の傷を深めないためにできることは何かということを、「トラウマ」を周縁化せず、絶対化もせず一人ひとりが実践できるようにしていくものです。心の傷という眼鏡で物事を捉え直し、起こっていることを捉え直していく。起こっていることは危機に対してのその人なりの対処でもあり、社会の構造的問題により起こっているものだと認識することでもあります。そして、何が問題かを捉え直すことでもあります。同時に、人のレジリエンスをエンパワーし、人の物語の再生・再構築が可能となる安全の土台を社会につくっていくものでもあります。安全の土台をつくっていくというのは簡単ではありません。だからこそ、子どもの暮らす社会状況や文化に何らかのかたちで関わる市民一人ひとりが学び、実践できることが必要です。同時に治療が必要な傷と資源がつながる状態をつくる。そうやって、傷の治癒機能や予防機能が上がる、レジリエンスのある社会をつくっていく一端を担うことが、これから求められていくのではないでしょうか」
Text by Masaki Koike, Edit by Kotaro Okada