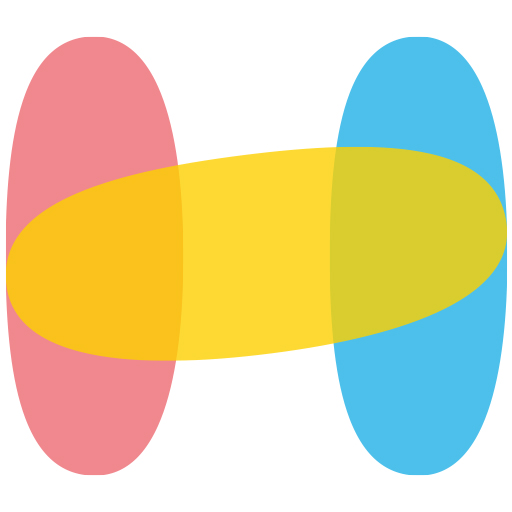あらゆるバックグラウンドをもつ社会的マイノリティを包摂し、誰もがその恩恵を受けられる社会を目指す「インクルーシブデザイン」。多種多様な患者を受け入れるべき社会インフラたる病院にとって、その考え方を取り入れることは重要でしょう。
インクルーシブデザインの現在地と未来、そして医療への応用可能性を考えるため、日本におけるインクルーシブデザイン推進の第一人者である、 九州大学大学院芸術工学研究院教授の平井康之さんにインタビューしました。
前編では、インクルーシブデザイン自体の定義と現在地から、実際の医療への応用例まで概説。続く後編では、具体的にインクルーシブデザインを取り入れた病院──「インクルーシブホスピタル」の可能性に迫っていきます。
インクルーシブデザインは“ふりかけ”ではない ── 「最初から」踏まえることの重要性
インクルーシブデザインを実践していくにあたり、まず考えなければならないのは、「最初から」その観点を考慮することだ、と平井さん。
「インクルーシブデザインはプロセスの最後の最後で考えればいいと思われているから普及しないんです。本当は、プロセスのはじめに踏まえることが必要です。その認識が広まらないと、変わらないと思います」
プロセスの最初からインクルーシブデザインが実践されていた例として、平井さんは東京都立砧公園内の「みんなのひろば」を挙げます。2020年3月、この広場に障害のある子もない子もみんなで遊べる複合遊具が設置されました。
ダウン症の息子を持つアナウンサー・龍円あいりさんが、アメリカで健常者の子どもと障がいのある子どもが一緒に遊べる「インクルーシブ・プレイグラウンド」を目にし、日本にも同様の場所をつくりたいと決意。都議会議員に立候補し、実現まで漕ぎ着けたのだと言います。以降、NPO法人未来をつかむスタディーズ「みらスタ」をはじめ、全国各地で同様の事例が増えつつあります。
「今はみんな、公園にはブランコや滑り台があるのが普通だと思っているじゃないですか。でも、そう思っている間は何も変わらないんです。異なるスタンダードがあると認識されて初めて、『そうか、私たちは裸の王様だったんだ』と気づくわけです」
とはいえ、固定観念を変えることは容易ではありません。新たなスタンダードは、勝手には生まれない。活動家的な志向性を持った人がどんどん事例をつくることで、少しずつ社会に浸透していくと平井さんは語ります。
平井さんが例として挙げたのが、家具に3Dプリンターでつくったアタッチメントを付けることで、障がいのある人も使いやすくするイケア・イスラエルのプロジェクト「ThisAbles」です。この事例を踏まえて、変革が容易ではない既存システムを小さく変えていくことの重要性を指摘されました。
「ケア=サポート」ではない ── ユーザーと「共に行動する」ことで見えるもの
実際にどのようなプロセスを経ることで、開発者のバイアスを取り除けるのでしょうか。
平井さんは有効な手段の一つとして、街中で日頃気づいていないものに気づくために写真を撮ることを挙げました。とはいえ「一番大事なこと」は、マイノリティの立場に置かれている人々と対話を重ねながら、一緒につくっていくことだと強調します。
「私の大学の学生が、『視覚障がいの人の料理のデザイン』というテーマに取り組んだことがありました。当初は『目が見えないから、包丁を使うのは危ないのではないか』と仮説を立てていました。しかし実際に、視覚障がいの方に協力いただいて調理現場を見に行ったら、みなさん慣れているので全く問題なくサクサクと包丁を使っていた。むしろ、お皿に盛り付けるときになかなか綺麗に並べられないことが課題だったとわかったんです。一緒に行動することで、初めて見えるようになることはたくさんあります」
その背景には、参画するステークホルダーの間における、同じ概念に対する捉え方の違いがあると平井さん。
たとえば、「ケア」という概念を一つ取っても、ケアする側は「サポートすること」と捉えている一方で、ケアされる側は自立を目標に、そのための支援を求めていることも少なくありません。「病気になったからケアしましょう、横になってください」と一方的に進めるだけでは、バイアスに気づけません、と平井さんは語ります。
いま必要な「インクルーシブホスピタル」宣言
こうしたインクルーシブデザインの実践における要諦は、もちろん医療への応用も可能です。
前掲のように「最初から」インクルーシブデザインを考慮したプロセスを実現するため、平井さんは「インクルーシブホスピタル」という言葉を用いながら、全体としてインクルーシブな病院を目指すことを提案します。
「神奈川県立生命の星・地球博物館をはじめ、博物館や美術館では『ユニバーサルミュージアム』を提唱し、展示のみならず保存や教育まで、あらゆる面でユニバーサルな施設をつくり上げている例があります。
同じように、病院自身がインクルーシブホスピタルであると宣言していくとよいのではないでしょうか。宣言したからといって、最初から完璧である必要はありません。いま何ができていなくて、その改善方法はこれから対話しながら考えていくとスタンスを明示すればいい。みなさん完璧を求めてアクションを踏みとどまりますが、一緒に良くしていくための宣言にすればいいんです」
平井さんはインクルーシブホスピタルが成立するために大事な条件として、「多様な人々が気持ちよく過ごせること」を提示します。
「人々は誰もがそれぞれお互いにバイアスを持っています。ですから、治療だけでなく患者さんの人生全体に目を向けたうえで、対話によってお互いのバイアスを理解して、同じ土俵に立てるコミュニティや場が必要です。ただ新しい病院ができたというだけでなく、常に変わっていく仕組みとして、インクルーシブホスピタルができると素晴らしいなと思います。そのためには、実際に病院の中にも入りながら、患者さんや医療従事者の方々と対話して見えてくるものの追究が必要です」
インクルーシブホスピタル実現には、ストーリーとジャーニーマップの構築が重要
インクルーシブホスピタルの実装を進めていく際、さまざまなステークホルダーのニーズに対して、いかにしてバランスを取っていくのかも課題です。ただ、平井さんは最初から完璧なアプローチを求めるのは望ましくない、と言います。
「視覚に障がいのある方、上肢に障がいのある方、下肢に障がいのある方、学習障がいのある方、高齢者の方、親子連れの方……できるだけ多くの方々に入ってもらえれば、新たな気付きを得られます。インクルーシブデザインにおいて、私はプロセスのデザインと成果物のデザインがペアになっていることを強調していますが、そうした気付きをその場で終わらせず、アーカイブして共有知として貯めていくことで、よりよいデザインが実現できるでしょう」
患者側、もしくは医療従事者の中に率先して先行事例をつくれる人がいるならば、彼/彼女らを病院設計のプロセスにインクルージョンできる、と平井さんは言います。
さらに、インクルーシブデザインに基づいて病院を設計することで、マジョリティと考えられている人たちの満足度も高まっていくと言います。たとえば、外に出られない子どもたちのためのヒーリング・アートとして、子ども病院の壁に絵を描くことがありますが、それによって病院にいる人全体のクオリティ・オブ・ライフが総合的に上がります。
参画性が広がれば、マジョリティ/マイノリティにかかわらず、全体的な創造性の発露につながるかもしれません。これは以前、『HCD-HUB』で取材した耳原総合病院・チーフアートディレクターの室野愛子さんが実践する、ホスピタルアートの考え方とも共鳴しています。
インクルーシブな病院の実装を推し進めるため、何らかのストーリーとジャーニーマップ(患者や医師、医療スタッフ同士の関わりの中でたどる、一連のプロセスを視覚化したもの)の構築が大切だと、平井さんはインタビューを締められました。
「小さいことでもいいので、『こういう人がいて、こういうことがあって、こういうことをやったらとても良くなった』というストーリーがあると、その重要性が人に伝わりやすくなります。ただでさえ忙しい医療従事者には、新しいことを始めて仕事が増えるのではなく、むしろ効率化につながる、と示すことが重要なんです。そのために自分の仕事のジャーニーマップをつくることも大切です。忙しいときこそ、一度俯瞰することで、『こんな無駄があった』『こんなプロセスが抜けていた』とわかり、興味を示してもらいやすくなると思っています」
社会インフラである病院にとって、あらゆる患者を分け隔てなく受け入れることは至上命題。だからこそ、インクルーシブデザインの考え方を取り入れ、インクルーシブホスピタルを目指すことはあらゆる病院に求められるでしょう。
もちろん、平井さんが繰り返し強調していたように、「いきなり完璧を目指さなくていい」。一人のデザイナーが0から100まで前もって設計するのではなく、多様な人々と一緒に“つくりながら考える”ことは、「デザイン」の本懐です。インクルーシブホスピタルを目指し続けるその姿勢こそが、多様な人々を包摂する病院の実現につながっていくのではないでしょうか。
Text by Masaki Koike / Edit by Kotaro Okada