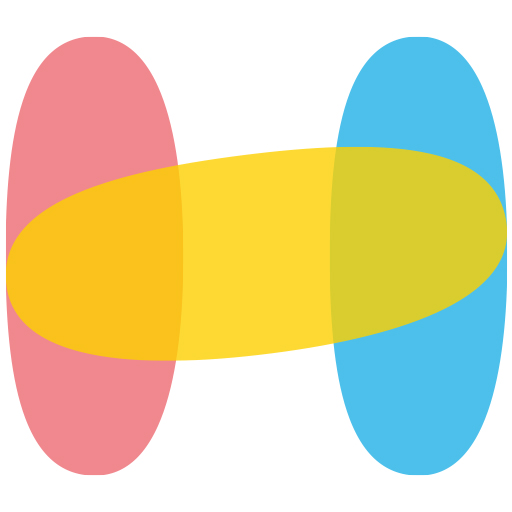「生活の中に人の死を戻そう」
暮らしから「死」が遠ざけられていると言われている現代。このようなスローガンを掲げ、患者自身の「ものがたり」をベースとした終末期医療のあり方を探り続けてきた先駆的な医師。今回インタビューした佐藤伸彦さんは、そんな方です。
2009年に医療法人社団ナラティブホームを立ち上げ、在宅療養支援診療所「ものがたり診療所」にて、患者さんへの終末期医療に取り組んできた佐藤さん。2020年には、従来の医療の枠組みを超えたより包括的な地域との関わりを目指し、賃貸集合住宅やレンタルスペース、カフェなども併設された「ものがたりの街」を創設しています。
前編記事では、EBM(Evidence Based Medicine)を補完する臨床手法として近年注目を集めている、「NBM(Narrative Based Medicine)」の先駆者としての活動の軌跡と、背景にある想いを聞きました。後編記事では、患者固有の「ものがたり」を大切にする医療を実践し続けてきた佐藤さんの、生と死にまつわるより深層的な価値観に迫っていきます。佐藤さんは人の死を、人の生を、どのように捉えているのでしょうか?
死を迎えるとき、グリーフケアは終わっていなければならない
── 佐藤さんは、人の「死」というものをどう捉えているのでしょう?
「人の死とは何なのだろう」と数十年ずっと考えてきたのですが、死んだらどうなるかなんてわからない。死んだ後どうなるかは人それぞれ、100人いれば100通りの考え方があっていいのだと思います。 むしろ私たちが見なければいけないのは、死ぬまでどう生きるかです。人の死というものは、関係性の中で決まってくるのだと思っています。
息が止まること、心臓が止まることは、死そのものではありません。そのずっと手前から、関わる人々にとってその人の死は始まっている。死は事実ではなく、概念なんです。目の前で死んだことを確認しなくても、私たちは遠くの親戚が亡くなったことを実感できる。
私は「グリーフケアはしない」と日頃言っているのですが、それは高齢者医療の多くが、死を迎えるときには既に、グリーフケアは終わっていなければならないと思っているからです。ただし、自死や横死、災害死に対しては、いわゆるグリーフケアが必要だと思います。なぜなら、関係性が突然断ち切られてしまうから。しかし、私が携わっている終末期医療においては、死そのものにはあまり触れません。そこまでどうやって生きていくか、どのような関係性を紡いでゆくのかということを、徹底的に考えています。それがグリーフケアにもなっているのです。
人は死んだら、死者(使者)として生者の中に生まれるという感覚を、強く持っています。私は幼い頃に父を亡くし、もう当時の父の年齢を超えているのに、私の心の中にはまだ「とても怖くて頼りがいのある父」が生きている。ですから、グリーフというのは、自分の中に、死者が使者として生者の中に生まれる産みの苦しみなのだと思います。そうした生者と死者の関係性をつないであげることで、死というものを受け入れられるようになると考えているのです。
── 他方、現代社会では、日々の暮らしから死が覆い隠されている印象を受けます。
ナラティブホームのビジョンの一つに「生活の中に人の死を戻そう」というものがあります。もちろん、病院で死ぬほうが安心だという方もいらっしゃいますし、それは尊重すべきです。でも、生活の中で死んでゆく良さもある。ですから私たちは、日々の暮らしの匂いや音、風景や音楽の中に、死を戻してあげようという取り組みをしているんです。
正確に言えば、現代社会は死を隠しているというより、生を隠している。どうやって生きていくのかを、みんながきちんと考えられていないのだと思います。あらゆることが便利かつストレートに行えるようになり、人を待ったり、すぐには会えない人に手紙を書いたりといった“タメ”がなくなった。その結果いろいろな事や人に、想いを馳せて、自分の人生をきちんと考えていく能力が失われているように思えます。
自分がどうやって生きていくのかをしっかりと考えていけば、必ずそこに人の死というものも表れてきます。「メメント・モリ」という言葉もありますが、人の死を想うことは、最終的には生を考えることに帰着していくはずです。
「専門性を捨てられる」のが専門性
── 患者さんたちが「どうやって生きていくのか」にしっかりと向き合えるようになるため、佐藤さんが医療者として大切にしていることは何でしょう?
「その人の世界(ゲーム)で遊ぶこと」を大切にしています。人間は、人それぞれ違うルールのもとで生きているじゃないですか。靴下のたたみ方一つとっても各家庭で違う。みんな自分のルールや癖があって、もっと言えば価値観や人生観を持っている。患者さんにも、医療者とは違うそれぞれのルールがあるので、それをどうやって知るのかが大切です。
とはいえ、取扱説明書やルールブックのように、相手のルールがどこかに明示されているわけではありません。「さあ、あなたの人生を教えてください」と言ったって、誰もしゃべり ませんよね。でも、例えば一緒に畑仕事をしていると、「戦時中は本当に食べるものがなくてね」というように、昔の思い出を話し始めてくれます。畑仕事という相手のゲームの中で一緒に仕事をする(遊ぶ)ということから始まり、考え方(ルール)が変わっていくのです。
私はよく若手の医師に「先生はいつも遊んでいますよね(笑)」と驚かれます。一緒に畑仕事をする、縫い物や編み物をする、家に貼ってある歴代の当主の写真に映っている人が誰かを聞く…..そうして相手の生活(ゲーム)の中に入って遊んでいると、癖や価値観を見せてくれる。 相手の行ったことを遮って、「そんなのおかしいんじゃない?」とか、この患者さんは理解力がないとか、そんなふうに言ってしまうと、もう駄目ですよね。
── 医療者ではなく、一人の人間として接するということでしょうか。
おっしゃる通りです。自分のゲームとその人のゲームの境を越境することが必要で、そのためには医師としてではなく、人間として接しなければいけません。専門性を捨てられることこそが、私たちの専門性なんです。医師だとか看護師だとか、そんな属性は捨てて、相手のゲームを一緒に遊ぶ。でも、その人が目の前で「痛い」「苦しい」と言ったときには、サッと専門家としての自分に戻ってくる。そうやって臨機応変に自分の専門性を捨てられる人、専門性とそうじゃないところをうまく越境できる人こそが、真の専門家だと思っています。
ただ、相手のゲームで遊ぶときに、一つ注意しなければいけないことがあります。「相手のことは絶対にわからない」ということです。「あの人はああいう人だよね」と相手をわかったように思ってしまった瞬間に、ケアというものは終わってしまう。常に相手のことをわからないと思いながら、相手のルールは何だろうかと探す。それを受けて、「こんなときにこう思うのか。でも自分はこうだな」と自分のルールも見直していく。その繰り返しが必要だと思います。

ナラティブは「傾聴」ではない
── 「相手のゲームで遊ぶ」ということは、佐藤さんがナラティブホームでの実践において大切にされている、「患者固有の『ものがたり』に添ったケア」そのもののように思えます。
そうですね。ちなみに、もともとは患者さんが語る物語を「ナラティブ」という表現で指し示していましたが、最近はこの言葉を使わないようにしています。ナラティブという言葉自体はかなり普及しましたが、「相手の話を聞く」「傾聴」くらいの意味で使われていることも多い気がしています。語り手や聞き手に関係なく成り立つ「ストーリー」に対して、「ナラティブ」は誰がそれを語り、聞いていて、そのときにどういうインタラクションが起きるかがとても大事。日本語として対応する言葉がない。ですから、誤解を避けるため、「ナラティブ」という言葉は使わないようにしているんです。
代わりに私が使っている「ものがたり」は、ある事柄とある事柄を結びつけること、または結びつけたものとして定義しています。私たちは毎日、いろいろなこと同士を結びつけ、意味付けをしながら生きていますよね。それこそがものがたりであり、患者さんと最期の時間を過ごすときも、その人や周りの人々が最期の時間の中で死と生をどのように結びつけるのかを大切にしているんです。
── 患者さんやその周りの人々が意味付けをしていくうえで、医療者はどのような役割を果たすのでしょう?
私たちは「共同著作」という言い方をするのですが、意味付けをしているときに、そばにいて、少し手助けをしてあげるイメージです。ただ、その際に注意しなければいけないのが、書き換えてはいけないということ。「私はあなたのものがたりを聞きますよ」と、ずかずかと相手の中に入り、勝手にものがたりをつくってしまう、“ものがたりの侵襲性”には気をつけなければなりません。“良いものがたりをつくってあげる”のではなく、患者さんやその周りの人々が最期の時間でものがたりを紡いでいくために、そばにいて意味付けの作業に関与してあげるんです。
今の高齢者の方で、「死ぬのが怖い」という方はほとんどいません。それよりも、人の世話になって生きていかなければいけないことがつらい、という方々のほうが多い。だからこそ、繰り返しお話ししてきたように、いかに生きるかが大切。「今の生でいいんだよ」と思えて楽しく生きられるように、意味付けをするお手伝いをしていきたいと思っています。
サイエンスとものがたりの協働に向けて
── HCD-HUBでは「理想の病院って何だろう?」という問いを探求しています。「ものがたり」を大切にした医療を実践されてきた佐藤さんから、ヒントをいただけないでしょうか?
ものがたりの大切さを散々語ってきた後にこんな話をするのも何ですが、病院はサイエンスに特化すべきだと思います。中途半端にものがたりに取り組むのではなく、治療や診断に限って、まずは世界の最先端を極めてほしい。それを突き詰めていくと、必ずものがたりを考えなければいけないフェーズが来るはずです。サイエンスでは太刀打ちできない時が必ず来ます。
その時にものがたりのチカラが必要となります。病気を診るのではなく、人を診るのであれば、「サイエンス」と「ものがたり」のバランスをとることが必要な場面があります。二項対立ではなく、二項のバランスを考える私たちの思考の「タメ」を病院全体で持っている事だと思います。
うちの診療所では「命」チームと「いのち」チームで情報を共有して分かれているのですが、それぞれで流れてくる情報が全然違いますよ。病気や血液検査のデータなどは 「命」チームに全部流れていく一方で、「いのち」チームは写真を撮ったり、「今日はばあちゃん、こんなに食べました」「ばあちゃんちで飼っている猫です」といった、それぞれのゲームについての情報が流れたりしてくる。その二つを切り分けないと、うまくいかないですよね。
もちろん、いくら医学とは言っても、最終的には人と人とのかかわり合いなので、人にしかできないことを大切にしてほしいとは思います。廊下にゴミが落ちていたら拾うとか、患者 さんに会ったら挨拶をするとか。

── ものがたりの重要性を、既存のサイエンス側の医師たちに理解してもらうために工夫していることはありますか?
うちは総合病院から「終末期なので在宅でお願いします」と患者さんを引き取るのですが、亡くなったときに写真やビデオをつけて、先生方にお渡ししているんです。結局そうやって、楽しそうに笑顔で死んでいく姿を見せるしかないと思います。「ものがたりが大事」といくら理屈で言っても仕方がない。それを繰り返していくうちに、信頼関係ができて、より一層患者さんを任せていただけるようになるんです。
── ありがとうございます。最後に、ナラティブホームのような実践に他の人が取り組もうとしたら何が必要になるのか、アドバイスをいただけますか?
ナラティブホームの事業スキーム自体は、保険外のアパートをつくって、そこで終末期の人を看るという実にシンプルなものです。問題は、人との関わり方。どのように人と関係性を持って、最期の時間を看てあげればよいのか。それは地域によって全然違うと思うので、「◯◯モデル」のような枠組みはないと思うんですよ。ナラティブホームのやり方だって、そのまま他の地域で転用してもうまくいかないでしょう。ですから私は、ものがたり診療所を他の場所でチェーン展開していくつもりはまったくないんです。それぞれの場所で、チームやリーダーがどういうふうに考えて取り組んでいくのか、要はものがたりのミッションを共有できるかだと思います。何かあればいつでも連絡をいただきたい、対話をしたいと望んでおります。

Text by Masaki Koike, Edit by Kotaro Okada