みなさんは大切な誰かを失う悲しみや苦しみを経験したことがありますか?
かけがえのない家族や友人との別れほど辛いものはありません。しかし、死はいつか必ず訪れる不変の事実。最期の瞬間、私たちは実現できなかった何かを悔やみ悲観するのか、それとも、安らかな気持ちで亡くなるのか…。
今回お話を伺った緩和ケア認定看護師の河野さんは、日本の医療現場には死を敗北と捉える文化、多様な死に方を尊重できない医療者側の価値観が存在していたのではないか…、と考えます。
自分らしく生きること・死ぬこと、その人にとっての本当の幸せとは何かを追究していきたい。
死を疑似体験するワークショップ「人生の卒業旅行」。そこには、死を自然なことと受け入れ、オープンに語らう場がありました。

河野 佳代(こうの かよ)
緩和ケア認定看護師、緩和ケア病棟主任
認定看護師実習指導者、看護学校講師(終末期看護担当)
難病の1つである先天性神経線維腫症Ⅰ型を持って生まれたため、幼い頃から病と共に生きる事の意味や、受容過程の難しさ、自分らしい生き方について考え続けている。
これから訪れる多死社会の中で、ご本人や家族、そして関わる全ての医療介護従事者の苦しみが少しでも和らぐように。
生き方や死について自然に語り合い分かち合える、そんな新しい文化が生まれる事を願って活動を始めた。
意思の尊重、生命の尊厳
日本において90年代後半から本格的に発展してきた緩和ケア。その在り方には明確な定義があります。
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患・病気によっておこる様々な課題に直面する患者やその家族に対して、痛みやその他の体の辛さ、心の辛さ、社会的な辛さ、そして生きている意味を失うスピリチュアルな辛さを早いうちから発見して、治療を行うことによって、苦しみを予防して和らげる。それによってQOLを維持・向上させるアプローチである
国立がん研究センター webサイト「がん情報サービス」
河野さん
“緩和ケアの考え方は、人間の生き方、あるいは本質だと思いました。仕事や自分の役割を失う社会的な辛さや、生きる意味を問う 根源的な辛さへも、しっかりと寄り沿えるアプローチをしていくことで、人生の質を最後まで支える。まさにこれだと思いました。”
今では患者本人に疾患の告知するのが一般的ですが、十数年前までは家族に告知して治療の判断を委ねるケースがほとんどでした。医者との関係性に遠慮して本当の気持ちを言えない人、あるいは言っても叶えられない例が沢山あったそうです。
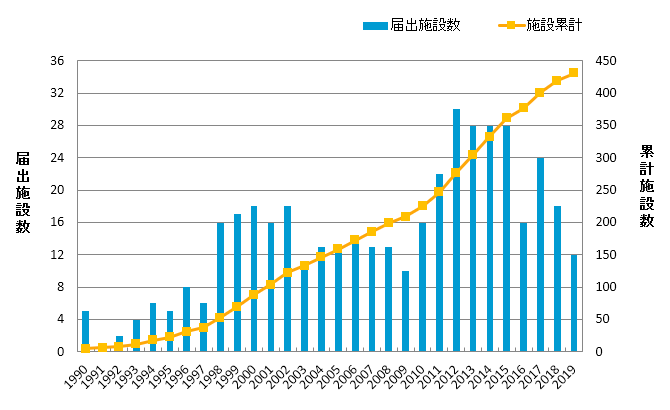
河野さんは一般病棟の看護師をしていた頃から何度も看取りを経験してきました。そんな中、ある女性と出会います。
河野さん
“その女性に残された時間は数カ月だったのですが、その方が臨んだのは、治療をせず自然な姿で死んでいくことでした。様々な医療機器が周りに増えていく中で私に渡してくださった手紙は「自分の最期はこういったことはしないで欲しい」という念書でした。しかし結局のところ、本人の意思を尊重するのではなく、一人息子さんの「おふくろ頑張って欲しい」という願いと、「病院に居る限りできる治療は全てやっていく」という主治医側の2つの意見が優先されてしまいした。本来であれば、その人が願う生き方を支えるために医療側が考えてフォローするべきだと思うのですが、なぜか生き方の主導権は医療者側にありました。患者さん本人の意思はどのようにすれば叶えられるのかと色々と考えました。”
「命の過ごし方を医療職員にはどこまで決定する権利があるのか」という問題意識が、緩和ケアの「生命を尊重して、死ぬことを自然なこととして認める」という指針と重なり、認定看護師の道を進むことになりました。
河野さん
“死なせないようにする医療ではなく、人は必ず死んでいくのだから、それを自然なこととして、その過程で 起きる苦しみは和らげようという考えが自分のポリシーにぴったりと合いました。そうして緩和ケアの認定を目指すことになりました。緩和ケアを選んだのは、一生かけて学べることだと思ったからです。”

緩和ケア病棟の朝日。患者と一緒に初日の出を見た思い出がある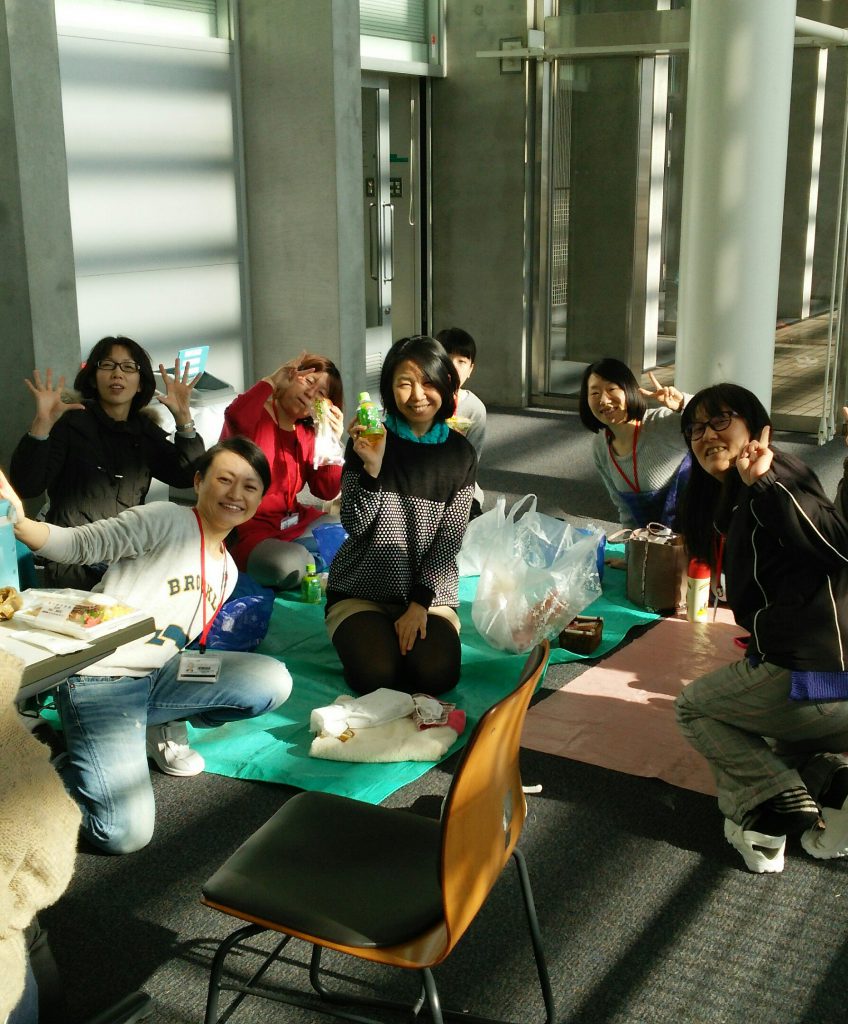
認定教育課程の仲間たちと撮影
自分の過去と存在を受容するために
人生の数があれば同じだけの最期の在り方が存在しますが、それは大きく2通りに分けられるそうです。
「ありがとう」と言いながら穏やかに感謝して亡くなっていける人と、「こんなはずじゃなかった」と人生を後悔しながら怒りの中で亡くなっていく人。
河野さん
“やはり怒りの感情の奥には本当の願いが隠れていることが多いのです。「怒り」をひらがなで書いてひっくり返すと「りかい(理解)」となりますよね。怒っている多くの人に共通していたのが「自分の人生こんなはずじゃなかった」「今まで何のために生きてきたのか」「誰かにこの苦しみを分かってほしい」という想いでした。自分の生きてきた過去を容認できず否定してしまう時が一番苦しいのです。未来を見つめると死が待っていて、過去を振り返ると後悔しかない人生ばかりが思い出される。そうすると、今を生きている意味を見失ってしまいます。”
この場合は本人だけではなく、残された家族や医療従事者も同様に苦しむ、負の連鎖が生まれてしまいます。

“一方で、自由を失っていく中でも、今あるものにフォーカスして「今日も天気が良かった」「花が咲いていた」と小さなことに喜びを見出しながら生きていける人もいます。その人達に共通しているのは「色々なことがあったけれども、人生まんざらではありませんでした」と自分に丸を付けられていることでした。”
この2つの死に方の真理こそ、死を疑似体験するワークショップの目的なのです。
河野さん
“人生の最期になって「あなたらしさを支えます」と言われても、「私らしさとは何なのだろう?」と戸惑われる方がとても多かったと思うのです。しかし、今回のコロナの件のように何か大きなきっかけがあると、「自分の人生が永遠に続くものではない」「いずれ終わるのだ」と感じます。終わりが見えてくると、それまでよりも死を自分ごととして真剣に考えるようになると思います。「どうすれば自分らしく生きることを一緒に考える場はつくれるか」と考えた時に思い出したのが「死の体験旅行」でした。”
前半部では、死の受け入れ方や意思決定に関する課題、そして緩和ケアの本質をご紹介しました。数多くの患者さんを看取ってこられた河野さん自身の体験談が「人生の質を最期まで支える」というケア哲学の重要性を物語っているようでした。
さて、後半部ではワークショップを通して伝えたいメッセージをご紹介したいと思います。



