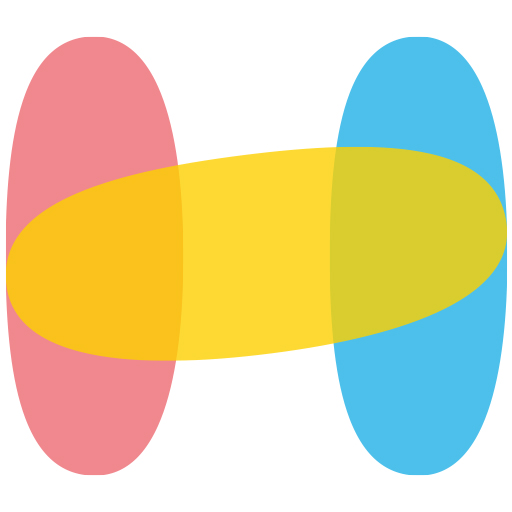診断・治療にとどまらず、病院の果たせる役割を広げていくことを模索するホスピタルアート。院内に芸術作品を設置することで、患者やその家族、そして医師や看護師のウェルビーイングへの寄与を目指します。その数少ない国内事例の一つが、大阪府堺市の耳原総合病院です。
HCD-HUBでは、同院のチーフ・アートディレクターを務める室野愛子さんにインタビューを実施。前編記事では、実際に置かれているホスピタルアートの全容、その背景にある室野さんの「一人ひとりに表現者になってほしい」という想いを解き明かしました。
彼女はなぜ、人々の内発性を信じ、自己表現の補助線を引くことを徹底的に重視しているのでしょうか? 後編記事では、その信念の背景にある、室野さんの生い立ちを探っていきます。学生時代の「忘れられない体験」、それらを乗り越えて現在に至る室野さんが見据える、医療や病院の未来像とは?
とある衝撃の体験
幼少期より、絵を描くことが得意だったという室野さん。京都造形芸術大学に進学した彼女は、いかにして「医療」というもう一つの軸に出会ったのでしょうか。
手塚治虫の漫画『ブラック・ジャック』が好きだったこと、彼女の絵の才能の一番の理解者でもあったという祖父の入院時に「病室をもっと祖父らしい空間にしてあげたい」と感じたこと。室野さんが医療への関心を醸成する要因はいくつもありましたが、最も大きな影響を与えたのは、学生時代の、ある衝撃的な体験でした。
「19の頃、たまたま目の前で自死を目撃してしまったことがありました。その数時間前、よろけながら駅の階段をのぼっていく方を見かけました。私は心配に思って、少し下の位置で彼をいつでも支えられるように階段をのぼったのですが、そのときは何事もなかったんです。でも、用事を終えてその駅に戻ると、また同じ方を見かけました。やっぱりお元気がなさそうだったので、『何かあったらヘルプしなければ』と思って、近くに座っていました。でも、ふと視線を落としていたタイミングで、特急列車が悲鳴のようなとても長い警笛を鳴らしたんです。顔を上げると、その方が持っていたティッシュが空中にバーっと舞っている。重たい列車がやっととまったその跡には、ついさっきまで確かに助けになりたかった人が、灰色の雑巾のようになってしまっているのが見えたんです」
もちろん、その人の死の責任は、室野さんにはないと感じる人が大半でしょう。しかし、彼女は大きな衝撃を受け、「何か自分にできたことはなかったのだろうか」と無力感にさいなまれたといいます。あの方の傍に音楽やダンスや描くことや歌うことなど、何か表現手段があったとしても、自死まで追い詰められたのだろうか。それとも救われただろうか。そもそも、自殺とは本当に自ら殺しているのか、社会が追い詰めたのではないのか。であれば、私も社会の一員として何かすべきではないのか──そうして室野さんは、心身の健康を支えるアートを志すようになりました。

「面白そう、試してみよう」からはじまった
室野さんは2009年にNPO法人アーツプロジェクトの理事に就任し、その後もホスピタルアートの普及・実践を重ねてきました。そんななか、2013年に相談を持ちかけてきたのが耳原総合病院でした。
同院の新築計画を知った2年目の看護師が、当時の奥村伸二病院長に直談判し、ホスピタルアートを提案。「よくわからんけど、面白そうやな」。そう乗り気になった病院長のバックアップで、有志3名で職員全体にプレゼンをしました。その方々がさらなる勉強を重ねるべくアートミーツケア学会に参加した際、アーツプロジェクトの存在を知ったといいます。
室野さんも同院のプロジェクトに参画し、約10ヶ月ほどのお試し期間を経て、2013年には耳原総合病院のアートディレクターに就任しました。「プロジェクトの初期から地域住民の方も加わっていたことが、とてもユニークだったんです」。前編でも触れたように、同院は1950年に地域コミュニティと密接に関わりながら創設された歴史を持ちますが、その遺伝子はいまもなお受け継がれているのです。
もちろん「面白そう」だけでは、現在に至るまでの8年間も活用を継続することは難しいでしょう。病院経営の観点でもホスピタルアートの有効性が認められているのだろうと、室野さんは推察します。
「最近は病院もどんどん経営の効率化を求められるようになっていて、患者さんとの、そして職員同士のコミュニケーションを、できるだけ短時間で行わざるを得なくなっています。だからこそ、ギュッと凝縮した癒やしやコミュニケーションを実現してくれるホスピタルアートが役立っているのではないでしょうか。最初にお試しで手がけたアートプロジェクトは、『どんな病院をつくりたいか』を職員や地域の人々から引き出すものでした。その時も職員の潜在的な要望を引き出す影響を感じてもらえたように思います。正直、病院経営にどう役立つかは私にはわからないのです。でも前病院長、現病院長、理事長、管理者の方々の実体験の上で私やチームがまだここにいるという事実から、可能性と役割が明らかになっているのだと思います」


地域内のコミュニケーションを媒介する
当初より、ホスピタルアートの制作プロセスやそこで表現されるものについては、地域住民の参加や、地域性を反映することが重視されてきました。その背景には、設立時より耳原総合病院に根付く、地域住民との関係づくりを重視する組織文化があります。
大規模な病院は、元陸軍病院であることが少なくありません。しかし、耳原総合病院は、そのケースに当てはまりません。立ち上げを主導したのは、戦後の混乱期、無医村だった地域に「命は平等で、誰もが医療を受けられるべき」という志を持ち込んだ医師ら、医療者たち。住民の庭で産まれた卵だけをいただいて、無報酬で診察するかたちで立ち上げられた病院だといいます。当初より地域住民の中に溶け込んだ存在だったからこそ、現在でも病院内にとどまらず地域全体とかかわる文化が残っているのです。
「病院の中だけなく、地域住民の方々の率直なご意見を聞きながら、そして病気でなくても患者さんやご家族と関わりながら、地域住民とのコミュニケーションを媒介する役割を果たせるよう心がけています」
実際、前編で紹介した『虹色プロジェクト』の中で描かれた鳥の絵は、多くの患者や地域住民の意見を聞きながら制作したそうです。ホスピタルアートも業務改善も、室野さんは徹底して人々の内発性を重視しているのです。それは自己表現を助けるだけでなく、作品そのものの質も高めます。
「もちろん、芸術のための技術や表現方法などはさまざまにあります。しかし、私たちのアートはその重要性以上に表現したい中身と人に注目します。地域住民や職員、患者さんなどのご自身の物語や視点で捉えたものが、結果として一番、誰かの心を打つものになると思うんです。本当につらくて絶望的になると、あと一歩進むこと、一分一秒を生きることがとても苦しいときもあると思います。そのときに、目の前に見える希望の灯として、ホスピタルアートがあってほしい。そのためには、ご自身で表現してもらうのが一番いいと思っているのです」

「ほぐし、つなげる」場としての病院を
その後、室野さんが耳原総合病院にどのようなホスピタルアートを導入していったのかは、前編記事で詳述したとおり。さらに、直近でいえばコロナ禍という状況が結果的にホスピタルアートの重要性を高めているといいます。
「コロナ禍になってから、『ホスピタルアートをやっていてよかったですか?』と聞くアンケートを取りました。すると、8年前に導入した頃は55%しかいなかった『はい』と答えた人が、約70%まで増えたんです。パンデミック下、忙殺される日々において、交感神経が優位になることが多いからこそ、副交感神経が優位になる隙間の時間が大切なのではないでしょうか」
空の写真を募集する『クリアスカイプロジェクト』、院内のラジオ放送『ひかりの子ラジオ』、配膳トレーの『みみはら便り』……コロナ禍になって始めたアートプロジェクトもあったそうですが、「殺伐とした雰囲気の中ではとても良い影響を生んだようで、市民権を得つつある感覚があります」と室野さんは振り返ります。
ホスピタルアートは、地域社会における病院のあり方までをも変革しうる可能性を秘めています。室野さんは最後に、病院の理想の未来像について語ってくれました。
「せっかく治療して退院されても、同じ原因で戻ってくる患者さんが少なくない。現状、医療者が関与できるのはあくまでも何らかの症状が出てから、つまり下流だけです。でも本当は、健康増進や公衆衛生といった上流のプロセスにもっとフォーカスしたい、社会を治したいと考えている医療者は少なくありません。病院を、局所的な治療だけの場ではなく、社会全体をほぐし、つなげる発信場所にしていきたい。それぞれの物語を聞き、言葉にならないシグナルをキャッチできるホスピタルアートは、そのための一助となるのではないでしょうか」
プロのアーティストの作品を存分に活用し、緻密に熟慮された空間を設計する──「病院のアートディレクター」という肩書から、そのような姿をイメージする人も少なくないでしょう。
しかしインタビューを通して、患者、医師、職員、地域住民……病院、そして地域コミュニティにかかわるすべての人々が、言葉では掬いきれない想いを表現するための手段として室野さんが「ホスピタルアート」を捉えていることが伝わってきました。
学生時代の衝撃的な体験で感じた無力感を胸の奥底に秘めながら、診断・治療をするだけの場所ではなく、「ほぐし、つなげる」場所としての病院の実現に向けて奔走する──室野さんの挑戦は続きます。

Text by Masaki Koike / Edit by Kotaro Okada