患者や相談者を、地域の中で活動や人につなげる取り組み「社会的処方」。心身の健康やQOLの向上に貢献する活動として、各方面で注目されています。
西智弘さんは、「社会的処方」の本邦第一人者。病気の悩みや健康に関する⼼配ごとを相談できる場所として、2017年に『暮らしの保健室』を開設し、日々「社会的処方」を実践し続けています。一方、熊本県上益城郡甲佐町「谷田病院」が運営する『みどり保健室』も、地域の人たちの健康や福祉の向上・維持のために活動の幅を広げています。
西さんと谷田病院の事務部長・藤井将司さんを中心に、社会的処方やそれを波及させる保健室の意義、現状の手ごたえ、そして思い描く未来像について語ります。
過度の便利さゆえに、孤独感が増す社会
蓑田 唐突なんですが、最近、昔と今の社会の違いって何だろうと考えることがあります。昔は、人と人とのつながりがもっと強かったように思います。例えば、私が子どもの頃は、近所の人に叱られたりお節介を焼かれたりしながら、多くのことを地域社会で学んだと感じるんです。近年、つながりが希薄になったのは、コロナの影響などもあるのでしょうか。
西 僕の考えですが、現代は便利になりすぎているんじゃないでしょうか。人がひとりで生きていくための道具や手段が揃っていて、誰にも頼らずに生きていける環境になっていますよね。スマホやインターネットなどを使いこなせる、ある意味“強い人”はどんどん強くなっていき、そういうのが苦手な人は取り残されてしまっている。そんなふうにして、孤独を抱える人が増えていると感じます。蓑田さんの言う「お節介を焼かない社会」では、取り残されるのはその人の自己責任だ、で帰結してしまうんですよね。だから今、便利になりすぎた現代における、人と人とのつながりをリデザインする必要があるんじゃないでしょうか。互いにお節介を焼いたり、地域の人とつながることの大切さに改めて気づき、「楽しいじゃん」とさえ思える方向へ持っていけるといいですよね。

町に広げたいのは、誰もが健康に関われるネットワーク
藤井 西先生のおっしゃる、人と人とのつながりをリデザインしたものが、『社会的処方』ですよね。僕は西先生のご著書『社会的処方 孤立という病を地域のつながりで治す方法』を通じて、社会的処方の考え方に出会いました。それまで様々な町づくりに関わっていましたが、医療や福祉分野でのつながりが主でした。でも、「社会的処方ができる病院」を目指してからは、教育委員会や地域振興課、農政課など幅広い分野とのつながりが進んでいます。「こんな社会的処方を出したい」と思った時に、関わりのある誰かが教えてくれる、もっとも適切なところへつなぐことができる、という環境が整いつつあります。
西 谷田病院さんの『みどり保健室』の取り組みは、僕も注目しています。病院って、地域の人たちが集まりやすい場所なので、病院が社会的処方の主体となることには意義があると思います。とはいえ、必ずしも病院が中心となるべきだという訳ではないかなとも思います。病院が地域に開いていくだけでは多様な価値観には対応しきれないということを、僕も若い頃の経験を通じて痛感したので。大切なのは、つながれるポイントが町の中に点在していること。例えば、カフェや居酒屋や美容室、図書館なんかが社会的処方の拠点になってもいいと考えています。
藤井 たしかにそうですね。川崎市の場合、美容師さんやカフェのマスターがリンクワーカーの役割をになっていますよね。彼らが、「自分はリンクワーカーだ」と声高に掲げずとも、つながりが地域に広がっていくために、どのような工夫をされていますか?
西 『暮らしの保健室』が軸となって、町の様々な人や場所、そして病院へもつながっています。例えば、カフェの常連さんが癌になって、マスターに相談に来たとします。でも、直接的にはマスターが何かすることはできないですよね。だからマスターは、「悩みは聞いてあげられるけど、知り合いが『暮らしの保健室』っていうのをやっているから、行ってみたらどうかな」と提案する。この場合、カフェのマスターは立派なリンクワーカーですよね。リンクワーカーに関心がある人の背中を押してあげるという意味で、資格を作ったり研修を行ったりするのもいいでしょう。地域の特性によって、様々な進め方があっていいと思います。
藤井 「おせっかいちゃんステッカー」や「みどり保健室Tシャツ」なんかを作ってもいいかも(笑)。
柳原 いいですね。面白く楽しく、というのは継続するためにも必要かなと思います。
蓑田 まずは、関心のある人たちがつながるということが大事ですよね。横のつながりを意識しておくことが、誰かの悩みや相談ごとを、どこかへつなげることができるネットになるかもしれない。
西 イギリスのフルームという町には、お節介を焼きたい人が1,000人以上いるそうです。町の人口は25,000人ほどだから、全体の4〜5%くらいの人がリンクワーカー。町を歩いていると「調子はどうですか?」と声をかけられるそうです。人数もさることながら、そんなふうに話しやすい雰囲気や日常的な関わりなど、何かあった時にすぐにつながれるような関係性を作っておくことが大事なんだと思います。

解決方法を示すことが、最善の方法だとは限らない
藤井 健康や医療というテーマになると、たいていは、病院や医療者がどう解決するかという切り口で物事を考えますよね。でも、町の中には健康的なことに関わることができる人が、実はたくさんいると思うんです。例えば、先ほどのカフェのマスターの話のように、悩みが持ち込まれた際に「じゃあ、◯◯さんに紹介するね」という流れができていれば、町の中で悩みが循環しますよね。1人の人を支えるチームのようなものが、自然な形で町の中に存在している。そしてその中には医療者も含まれている、という仕組みがあるのが理想的かなと思います。
西 すぐに全てを解決する必要はなくて、共通課題が町の中で保持されているような状態でいいんじゃないでしょうか。「あの人がこういう悩みを抱えている」ということを町の人たちが知っている。そして、「みんなが心配しているよ」という雰囲気があれば、もしかすると当事者は、時間の経過とともに自力で解決できるかもしれないですよね。「見守ってあげる」という仕組みがあるだけで解決できることは、意外と少なくないと思います。解決してあげることをゴールにすると、関わるみんなが苦しくなるんじゃないでしょうか。
蓑田 なるほど。少しゆるいくらいでいいんですね。
西 すぐにパッと解決できることならいいですが、世の中、そう簡単には片付かない問題だらけですよね。だから、誰かの問題をみんなが一緒に抱えて見守り、その人が孤立しない状態を保つことが大事だと思います。当たり障りのないようにという思いから、あるいは良かれと思って、「こんなことをやってみたらどうですか」と解決方法を提示しちゃうのは、実はあまり良くないと思います。そうすると問題を抱えている人は、「私は1人でがんばらなきゃいけないんだ」と孤立してしまう。「問題を解決しようとしない」ということは実は、孤立孤独の問題を悪化させないことにつながると考えています。「一緒に考えてみよう」「いつでも悩みを聞くからね」という姿勢を示し続けることが大切なんじゃないでしょうか。
柳原 西先生が、そんなふうに考えられるようになったきっかけはありますか?
西 自分も同じような経験をした、ということはありますね。同僚に何かを相談した際に解決手段を提案されて、「それ、やったけど無理だったんだよな」「それは、その場しのぎでしかないんだよな…」など、相談した自分の方が苦しくなる、というような経験です。もちろん、今すぐに解決できる方法を探している人には、具体的なことを提案した方が良いこともあるでしょう。でも、『暮らしの保健室』に来るのは、そうじゃない人がほとんど。解決型思考で臨むと、その場では「ありがとうございました」と言ってはくれるけど、二度と来てくれなくなります。一度嫌な思いをしたら、二度目はないんです。それはつまり、こちらのコミュニケーションの取り方が良くなかったという結論になりますよね。
でも逆に、「あなたの悩みにずっと付き合いますよ」という姿勢で向き合うと、再訪してくれる。例えば3ヶ月とか1年くらい時間が空いてから、「お久しぶりです」と来てくれることもあります。その時に、「この前のアレですが、こういうふうに考えられるようになりました」と報告してくれたら、こちらは「そういうふうに考えられるようになったんですか」と応じて終わり。時間が経つと問題が小さくなったり、当事者の気持ちが変化したりすることってありますよね。だから、そういう対応でいいと思います。
柳原 「あそこに行ったら悩みを話せる」と思える場所があるのは心強いですよね。
藤井 ゴールを設定しないコーチングみたいな感じでしょうか。解決することを前提にコーチングをするのではなく、どこまでその人に共感するかを大切にして支援するんですね。
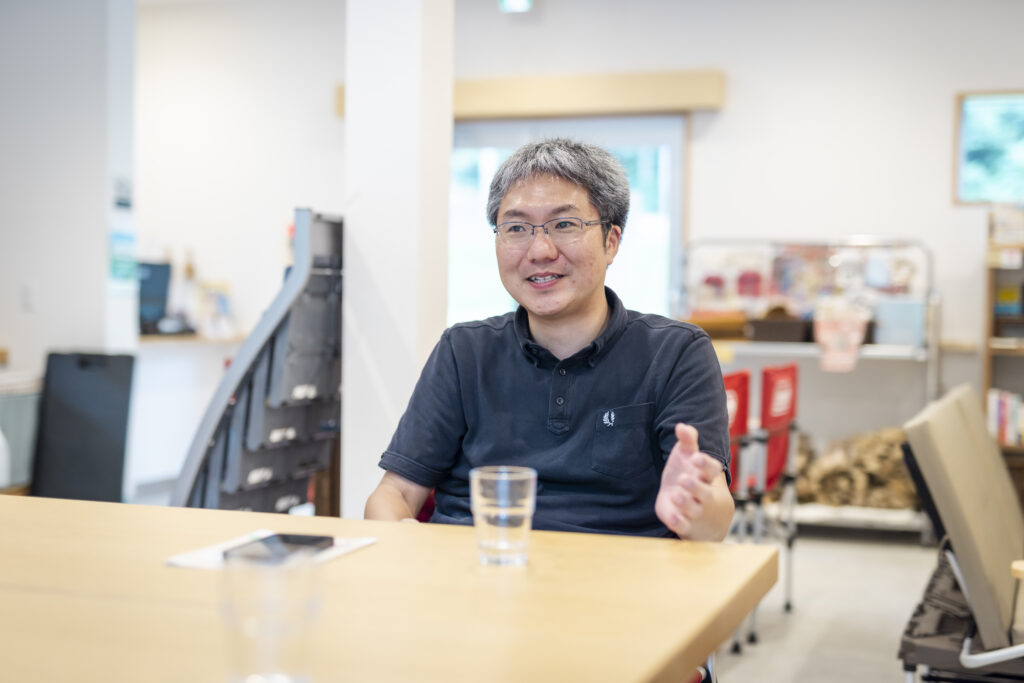
“ジャッジをしない”ことが、病院とは異なる保健室の役割
西 ジャッジをしないってことも大切ですよね。つまり、こちらが勝手に判断した文脈で話さない。例えば相談に来た人が、「こういうふうに考えられるようになったんです」と話したら、「そういうふうに考えられるようになったんですね」とだけ言う。その人が、「こういうふうに考えられるようになって、良かったです」と言ったら初めて、「それは良かったですね」と返す。世間一般で考えると良いだろうと判断できることであっても、相手より先んじて「良かったですね」とは言いません。こちらが勝手に「良いことだ」という文脈で話すと、その考えを相手に押し付けることになってしまいます。
例えば、ある女性の患者さんのお宅を訪問診療した際のことです。十分に食事を食べられないことを旦那さんが心配していましたが、次に訪問したら、「お寿司を3貫も食べてくれたんです」と旦那さんが報告してくれました。でも僕は、「3貫食べられたんですね」と答えて終わり。普通に考えれば喜ばしいことだし、旦那さんもうれしそうに話しているから「良かったですね」と言いたくなりますが、それを言うと、ご本人を苦しめることになってしまうんです。本人がどう思っているかわからないし、もしかしたら、がんばって無理に食べたのかもしれない。それがわからないうちから、「良かったですね」は口にしないようにしています。
他の例を挙げると、ゴミ屋敷で暮らしている人に対して、だらしがなくて精神的に問題があって…と先入観を持って接するのも、ジャッジをしていることになると思います。その人が精神を安定させるためには、ゴミに囲まれた状態が最適なのだとしたら、それを奪ってしまうことがベストだとは言えないですよね。だからまずはご本人に興味を持って、なぜそういう暮らしになったのか、その家で暮らすことをどう思っているのかを、丁寧に聞いていく必要があると思います。その上で、「こうすれば、もっときれいになると思いますよ」「その方がいいね」「じゃあ、こうしましょうか」と話を進めていきます。
藤井 もし、病院の診察室であれば対応は変わりますか?
西 そうですね。困っています、ということで訪れているのだとしたら、解決策を相談する流れになると思います。でも、ご自身の状況に困っていないのだとしたら、話を聞くことがメインになります。その過程で、目に見えている状況の裏に隠れている問題が浮き上がってきたり、それが、コアな部分のケアに結びついていったりする可能性もありますよね。
柳原 行けば誰でも無条件に話を聞いてもらえ、いつもは自分だけが抱えていることをシェアできる場所が、『暮らしの保健室』なんですね。
藤井 診察には主訴があるけれど、保健室の場合はそれがなくても誰でも利用できますよね。
柳原 とはいえ意識下では、このままじゃいけない、変わりたいと思っている人が来るんでしょうか。
西 そうとも限らないと思います。特に理由はないけれど、「私、こうなりました」「今、こうなってます」と定期的に報告をしに来る人もいます。ただ、言いに来る(笑)。
蓑田:地域の保健室活動の場合は、寂しいから来る人が多いように感じます。地理的な背景とか、高齢の人が多いとか、地域性や保健室ごとのカラーがあるのかもしれないですね。

住民の一人として地域に溶け込むことで、できる支援がある
藤井 保健室への敷居を下げるために意識していることはありますか?
西 医療者としてではなく、住民の一人としてそこにいるという意識でいます。専門的な知識を持った住民。それでも、お医者様に話しかけるなんて…という意識がまだ根強いようですが。それなら、保健室の担当者や心理士をはじめ、話しやすい人に話してもらえればいいと思っています。
柳原 医者として同じ町で生活するということは、地域の人が患者さんやそのご家族の場合もあります。西先生は、どんな付き合い方をしていますか?
西 医者として近所の方と付き合いがあることも少なくありませんが、僕は気にならないです。でもそれがストレスになる方は、無理をしない方がいいと思います。
柳原 私個人も西先生と同じスタンスなんですが、谷田病院は歴史も古く、地域の人たちから見守られていると感じます。患者さんとスタッフの距離が近いとか、どこの誰が今、困っているなんて情報をみんなが共有しているとか。“コミュニティーの力”で出来ることが残っている地域なんです。医療者も「同じ地域の中の人」という雰囲気があり、それは『みどり保健室』の強みなのではないかと思っています。こうした甲佐町ならではの“コミュニティーの力”を活かして、良いモデルを構築していきたいです。
西 それぞれの地域の特性に合ったやり方で、保健室が根付いていけばいいですね。それが社会的処方の多彩なロールモデルとして各地に広がっていくのも、遠い未来のことではないのだと思います。










